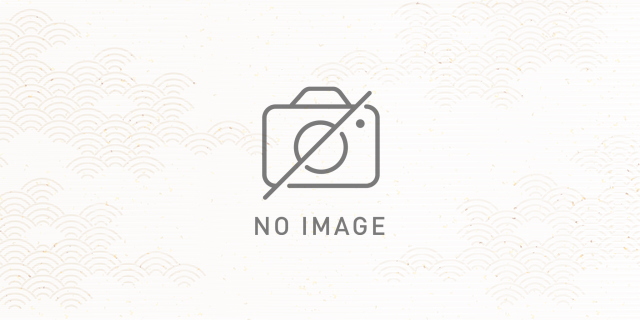作家一覧– category –
-

有田焼・伊万里焼
有田焼と伊万里焼は、17世紀に有田で誕生し、伊万里港から積み出されたことで共通の歴史を持ちますが、現在の産地と作風で区別されています。有田焼(佐賀県有田町): 主として白磁の美しさを基盤とし、柿右衛門様式の繊細な色絵や、古伊万里様式(金襴手... -

九谷焼
九谷焼(くたにやき)は、石川県加賀市周辺を産地とする、日本を代表する色絵磁器です。江戸時代前期に加賀藩の命により開窯されたのが始まりで、この時期の作品は特に古九谷(こくたに)と呼ばれ珍重されています。九谷焼の最大の魅力と特徴は、その豪華... -

美濃焼
美濃焼(みのやき)は、岐阜県東濃地方(主に多治見市、土岐市、瑞浪市、可児市)で製作される陶磁器の総称です。日本の陶磁器生産量の約半数を占める、国内最大の生産地です。最大の特徴は「特徴のなさ」とも言われる多様性にあります。定まった様式を持... -

益子焼
益子焼(ましこやき)は、栃木県益子町周辺で生産される伝統的な陶器です。江戸時代末期に窯業が始まり、当初は水がめや土瓶などの日用品を中心に制作され、関東の台所を支えました。大きな特徴は、地元の土を用いた、厚手でぽってりとした素朴で温かみの... -

磁器
磁器(じき)は、陶磁器の一種で、主に陶石やカオリンといった岩石を砕いたものを主原料とする「石もの」です。特徴として、1250℃以上の高温で焼かれるため、素地がガラス質化し、非常に硬く締まります。これにより、吸水性がほとんどなく、強度が高いため... -

陶器
陶器(とうき)は、陶磁器の一種で、主に山や田畑から採れる粘土(陶土)を原料として作られる「土もの」です。特徴としては、焼成温度が比較的低い(約800℃〜1200℃程度)ため、焼き上がりの素地が完全にガラス化せず、きめが粗く吸水性がある点が挙げられ... -

陶磁器
陶磁器は、陶器(土もの)と磁器(石もの)の総称です。主に粘土や陶石などの土の成分を原料とし、高温で焼き固めて作られます。 陶器は、粘土を主原料とし、比較的低い温度で焼かれます。素地には吸水性があり、軽く叩くと鈍い音がします。暖かみのある風... -

茶器
茶道具とは、茶の湯(抹茶)や煎茶の席で用いられる全ての器具の総称です。その中でも、特にお茶を点てたり、直接関わる道具を茶器と呼びます。抹茶の茶器の代表は、茶を入れておく茶入(濃茶用)や棗(なつめ・薄茶用)です。これに、抹茶を飲むための茶... -

茶掛
「茶掛(ちゃがけ)」とは、茶室の床の間(とこのま)に掛ける掛け軸のことで、茶道具の中で最も格が高く、重要とされる道具です。単に「軸」とも呼ばれます。茶掛は、その日の茶会の主題(テーマ)や亭主(主人)の客人へのメッセージを伝える役割を担っ... -

香炉
茶道において、香りを焚く道具には「香合(こうごう)」が中心的に用いられ、香炉(こうろ)は主に仏事や香道で使われますが、広い意味での茶道具・茶室のしつらえとして用いられることもあります。茶席の正式な流れでは、お湯を沸かす炭を継ぐ際に、香合... -

花入
「花入(はないれ)」は、茶室の床の間(とこのま)などに飾る花を入れる容器で、茶の湯における重要な装飾道具の一つです。花入は、茶会の趣向や季節感を表現する役割を持ち、掛物(かけもの)とともに客をもてなす空間の雰囲気を決定づけます。その種類... -

蓋置
「蓋置(ふたおき)」は、茶道で茶釜の蓋や、湯を汲む柄杓(ひしゃく)の合(ごう:水をすくう部分)を一時的に置くために用いられる、小さな台です。炉(ろ)や風炉(ふろ)のそばに置かれ、点前(おてまえ)を円滑に進めるための重要な役割を果たします... -

香合
「香合(こうごう)」は、茶道における香(こう)を入れておくための小さな蓋付きの容器で、茶道具の一つです。主に、炭手前(すみまえ)で、湯を沸かす炭に火を移す際にくべる香木や練香(ねりこう)を収納する役割があります。この香をたくことで、茶室... -

鉄瓶
「鉄瓶(てつびん)」は、鉄製の湯沸かしで、茶道で湯を沸かす「茶釜(ちゃがま)」を小型化し、注ぎ口と持ち手(鉉:つる)を付けたものです。江戸時代後期に、茶釜よりも手軽に使える道具として誕生しました。茶道においては、正式な席で使われる茶釜に... -

風炉
「風炉(ふろ)」は、茶道で茶釜(ちゃがま)をかけてお湯を沸かすために用いる道具です。通常、畳を切った「炉(ろ)」を用いる寒い季節(晩秋から春)に対して、初夏から秋の時期(5月〜10月頃)に使用されます。客の座から火元を離すことで、見た目にも... -

茶釜
「茶釜(ちゃがま)」は、茶の湯(茶道)において、抹茶を点てるためのお湯を沸かすために用いられる、最も重要な茶道具の一つです。主に鉄で作られており、火にかける場所によって名称が変わります。畳を切って作った「炉(ろ)」に据えるものが一般的で... -

棗
「棗(なつめ)」は、主に茶道で抹茶を入れるのに使う茶器の一種です。木製の漆塗り(うるしぬり)でできた蓋付きの容器で、特に薄茶(うすちゃ)を入れる「薄茶器(うすちゃき)」の代表的な形として広く知られています。その名前は、形が植物のナツメの... -

水指
水指(みずさし)は、茶席において「清らかな水」を貯えておくための容器です。茶を点てる際に、釜へ水を補給したり、茶碗や茶筅を清めたりする水として用いられます。単なる実用品に留まらず、茶室の床の間や棚に置かれることで、空間の景色を構成する重... -

茶杓
茶杓(ちゃしゃく)は、茶入から抹茶をすくい取り、茶碗に入れるための細長い匙(さじ)です。竹を削って作られるものが主流であり、その一本の竹の中に「侘び寂び」の美意識と茶人の心が凝縮されています。素材と形状: かつては象牙などが用いられました... -

茶入
茶入(ちゃいれ)は、茶道で濃茶の抹茶を入れておくための陶磁器製の容器です。漆器の棗(なつめ)が主に薄茶用であるのに対し、茶入は濃茶の席で使われ、その歴史的背景から茶道具の中でも特に格式高いものとして重んじられてきました。室町時代から戦国... -

茶筅
茶筅(ちゃせん)は、抹茶とお湯を均一に混ぜ合わせ、きめ細かな泡を立てるために不可欠な竹製の道具です。茶道のために特化して作られた機能美を持つ道具であり、茶の湯の風味を左右します。役割と構造: 主な役割は抹茶を攪拌すること。一本の竹を細かく... -

茶碗
茶碗は、茶道において抹茶を点て、客に供する最も重要な主役となる道具です。単なる器ではなく、亭主の趣向や「侘び寂び」の美意識を表現する鑑賞の対象とされます。産地により唐物(中国製)・高麗物(朝鮮半島製)・和物(日本製)に大別されます。特に... -

茶道具
茶道具は、茶道における「侘び寂び」の精神と美意識を体現する道具一式で、単なる実用品以上の芸術品として重要視されます。茶会では、亭主の心遣いや趣向を客に伝える役割を担います。抹茶とともに中国から伝来した当初は豪華な唐物が中心でしたが、千利... -

中国掛軸
中国の掛軸は、北宋時代に起源を持つとされる、書・画・詩・印が一体となった総合芸術です。元々は仏教の布教や礼拝の対象である仏画の持ち運びのために、巻物状の形式が発展しました。最大の特徴は「書画同源」の思想に基づき、絵画に詩や書が添えられ、... -

掛軸
掛軸(かけじく)とは、書や東洋画などを布や紙で表装し、床の間などに掛けて鑑賞できるように仕立てた日本の伝統的な装飾品です。下端の軸木に巻きつけて保管できます。もとは中国から伝わり、仏教の礼拝対象として使われていましたが、日本では茶道の普... -

インテリアアート
インテリアアートとは、空間を彩り、個性や雰囲気を演出するための芸術作品を指します。絵画や写真、ポスター、オブジェ、ファブリックアートなど形はさまざまですが、共通する目的は「空間をより豊かに見せること」です。壁や家具の色調、照明とのバラン... -

書画
書画(しょが)とは、東洋美術において、書(文字を芸術として表現したもの)と絵画を総称する言葉です。特に、中国や日本などで発達しました。書画は、文字のみの作品や、水墨画などの絵画作品自体も広義に含みますが、筆墨を共通の用具とし、漢字の持つ... -

動物画
動物画とは、動物の姿や生態、またはそれらが持つ象徴的な意味や物語を描いた絵画です。単に生き物を写実的に描く博物画(ずかん絵)のほか、日本には古くから神話や伝説の動物、あるいは人々の畏敬や親愛の念が込められた象徴的な動物(龍、虎、鶴など)... -

美人画
美人画とは、女性の容姿や内面の美しさを描いた日本の絵画ジャンルを指し、江戸時代の浮世絵に始まり、明治期以降に近代日本画の一つのジャンルとして確立されました。単に女性の姿を描くだけでなく、その時代の美意識やファッション、生活様式を反映する... -

水墨画
水墨画とは、墨一色、または淡彩で描かれる東洋の伝統的な絵画形式です。墨の濃淡、にじみ、ぼかしなどの技法で色彩や立体感、そして物事の本質を表現する点が特徴で、中国の唐代に始まり、日本にも伝来して独自の発展を遂げました。「墨に五彩あり」とい... -

山水画
山水画とは、山や川などの自然の風景を題材とした東洋絵画のジャンルです。単なる風景描写ではなく、作者の心情や思想を表現するために心の中で再構成された創造的な景色が描かれ、理想郷や精神性を追求する特徴があります。主に水墨で描かれることが多く... -

人物画
人物画(じんぶつが)とは、人間を主題とした絵画の総称で、風景画や静物画などと対比されるジャンルです。単に人の外見を描くだけでなく、内面、感情、社会的な背景、そして物語性などを表現する役割を持ち、肖像画、風俗画、歴史画など、さまざまな種類... -

花鳥画
花鳥画(かちょうが)とは、花、鳥、虫、獣、魚介などを主題とした東洋絵画の一ジャンルで、自然界の調和や季節の移ろいを表現する伝統的な画題です。中国唐時代に独立した主題となり、日本では平安時代から描かれ始め、大和絵の技法を取り入れて独自の発... -

仏画
仏画は、仏教の教義や仏、菩薩、守護神などの姿を視覚的に表現した絵画です。礼拝の対象として、また仏教の教えを人々に分かりやすく伝える手段として制作されました。仏像と並んで重要な仏教美術であり、寺院の壁画や掛軸、版画など様々な形式があります... -

チェスト
家具の「チェスト」は、主に衣類や小物を整理・収納するための引き出し式収納家具のことです。日本語の「整理タンス」とほぼ同義で使われますが、チェストは洋風のデザインや現代的な収納家具を指す傾向があります。複数の引き出しが段になって構成されて... -

デスク
家具の「デスク(机)」は、主に仕事や勉強などの個人作業を行うために設計された家具です。一般的に、複数人で使用する「テーブル」と区別され、一人が集中して作業しやすいよう、天板のサイズや高さが設定されています。機能性を重視しており、文房具や... -

テーブル
家具の「テーブル(卓)」は、平らな天板を脚や支柱で支え、食事や作業、物を置く台として使われる、生活に欠かせない家具です。用途によって種類が分かれ、食事用のダイニングテーブル、リビングのソファと合わせて使う背の低いローテーブル(センターテ... -

ソファ・チェア
「ソファ」と「チェア(椅子)」は、どちらも座るための家具ですが、その目的や設計に違いがあります。ソファは、主に身体を休め、ゆったりと寛ぐことを目的に設計されており、複数人で座れる広さや高いクッション性を持つものが一般的です。リビングなど... -

アンティーク雑貨
アンティーク雑貨とは、製造から100年以上が経過した、歴史的・美術的価値を持つ古い雑貨のことで、一般的に「100年を経過した手工芸品・工芸品・美術品」と定義されています。機能的な価値だけでなく、道具としての歴史や美術品としての価値が認められる... -

現代アート
現代アート(コンテンポラリーアート)とは、第二次世界大戦後の1950年以降から現在までに制作された、社会や時代の問題提起、思想、コンセプトを重視し、絵画・彫刻以外の写真、映像、インスタレーションなど多様な表現方法を用いた前衛的な芸術ジャンル... -

シルクスクリーン
シルクスクリーンとは、メッシュ状のスクリーン(版)にインクを透過させ、素材に印刷する「孔版印刷」の一種です。かつてはシルク(絹)が版の素材だったことからこの名前で呼ばれますが、現在ではナイロンやテトロン、ステンレスなども使われています。... -

リトグラフ
リトグラフとは、平らな石や金属板に脂肪性のインクで絵を描き、水と油の反発作用を利用して印刷する「平版画(へいはんが)」の技法です。1798年にドイツのアロイス・ゼネフェルダーが発明し、描画した内容がほぼそのまま紙に転写されることが特徴で、ク... -

版画
版画とは、版(木・石・金属など)にインクを付け、紙に圧力をかけて転写し、同じ絵柄を複数枚作成できる技法、およびその技法で作られた絵画作品のことです。版画の大きな特徴は「間接性」と「複数性」であり、絵画のように直接描くのではなく版を介する... -

歴史画
歴史画とは、歴史上の出来事や神話、伝説、宗教的な物語などを主題とした絵画のジャンルです。視覚芸術を通じて物語を伝え、時には教訓やメッセージを表現する役割も持ちます。特に西洋美術においては、アカデミズムの時代に肖像画や風俗画、静物画よりも... -

宗教画
宗教画とは、宗教上の物語、人物、教えを視覚的に伝えるために描かれた絵画のことです。昔は識字率が低く、書物で宗教を広めるのが難しかったため、絵が絵本や教科書のように役割を果たし、人々に信仰心を深める手段となりました。キリスト教や仏教など、... -

抽象画
抽象画とは、具体的な形や対象を写実的に描かず、色、線、形といった造形的な要素自体を表現の手段とし、画家自身の感情や内面世界を表現する絵画です。同じ作品でも観る人によって解釈が異なり、観る人の想像力に委ねられるため、自由な鑑賞が可能です。... -

肖像画
肖像画(しょうぞうが)とは、特定の人物の顔や姿を写実的に描いた絵画のことです。単に外見を描くだけでなく、その人物の内面、社会的地位、文化的背景を表現する重要な芸術形式でもあり、写真がなかった時代には、人々の生きた証を残すための貴重な手段... -

静物画
静物画とは、花、果物、食器、楽器など、動かない自然物や人工物を題材として描いた西洋画のジャンルです。画家がこれらの対象物を自由に配置・構成して描くのが特徴で、画面構成や質感を追求する目的で制作されます。中世ではあまり描かれませんでしたが... -

風景画
風景画とは、山、川、森、街並み、空などの自然や都市の景観を主題として描いた絵画です。自然の美しさや壮大さを表現し、時に感情や文化的背景を反映させることを目的としています。西洋美術では近代になって独立したジャンルとして発展しましたが、東洋... -

水墨画
水墨画とは、墨を主顔料に、墨の濃淡、潤渇、ぼかし、にじみ、かすれといった技法を用いて、色彩がなくても立体感や色彩感を表現する東アジアの伝統的な絵画様式です。単なる見た目を再現するのではなく、物事の本質や作者の主観、内面の精神性を表現する... -

日本画
日本画とは、明治時代以降に「西洋画」が伝わったことでそれまでの日本の伝統絵画を指すようになった名称で、岩絵具や墨などの伝統的な画材を和紙や絹の上に毛筆で描くのが特徴です。岩絵具は鉱石を砕いたもので、金箔表現や、岩絵具の粒子の重なりが独特...