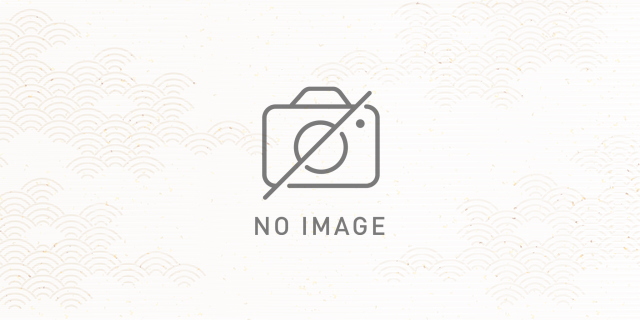作家一覧– category –
-

増村益城
買取相場10,000円~300,000円 増村 益城(ますむら ましき、1909-1996)は、昭和から平成にかけて活躍した漆芸家です。特に、中国から伝わった存星(ぞんせい)の技法を研究し、日本の漆芸に取り入れた第一人者として知られています。修行と作風: 漆芸家の... -

前大峰
前 大峰(まえ たいほう、1914-1977)は、昭和時代に活躍した漆芸家です。特に、石川県輪島(わじま)の伝統的な漆器技法である沈金(ちんきん)の分野で、近代的な表現を確立しました。修行と作風: 輪島で沈金を学び、伝統的な線彫り技法だけでなく、多様... -

堆朱楊成
堆朱 楊成(ついしゅ ようぜい)は、室町時代から江戸時代にかけて代々続いた漆芸家の家系です。彼らは主に堆朱(ついしゅ:彫漆の一種)の技法を専門とし、特に江戸時代を通じて幕府の御用を務めました。技法: 堆朱とは、素地(器の土台)に朱色の漆を何... -

白山松哉
白山 松哉(しらやま しょうさい、1853-1923)は、明治から大正時代にかけて活躍した漆芸家・蒔絵師です。本名は細野福松。修行と活動: 11歳で蒔絵師の小林好山に、後に彫漆や螺鈿を蒲生盛和に師事し、多様な技術を習得しました。青年期には起立工商会社に... -

小川破笠
小川 破笠(おがわ はりつ、1663-1747)は、江戸時代中期に活躍した漆芸家・蒔絵師です。多才な芸術家: 俳諧(松尾芭蕉門下)、土佐派の絵画、肉筆浮世絵なども嗜むなど、マルチな才能を発揮しました。独自の技法: 蒔絵の伝統的な手法に飽き足らず、漆器面... -

大場松魚
大場 松魚(おおば しょうぎょ、1916-2012)は、昭和から平成にかけて活躍した漆芸家で、特に蒔絵の分野で高い評価を得ました。師事と技法: 石川県金沢市出身。父に師事した後、蒔絵の松田権六(まつだ ごんろく)に内弟子として学びました。奈良時代に栄... -

池田 泰真
池田 泰真(いけだ たいしん、1825-1903)は、幕末から明治にかけて活動した漆工家・蒔絵師です。師事と作風: 11歳で漆芸の大家である柴田是真(しばた ぜしん)に入門し、25年近く内弟子として研鑽を積みました。是真の一番弟子と言われ、師から受け継い... -

研ぎ出し蒔絵
研出蒔絵(とぎだしまきえ)は、蒔絵の技法の中で、文様を漆の層に埋め込み、表面を研ぎ出して光沢を与えることに特徴があります。技法の工程:まず、文様となる部分に漆で絵を描き、漆が乾かないうちに蒔絵粉(金粉や銀粉など)を蒔きつけます。粉が定着し... -

高蒔絵
高蒔絵(たかまきえ)は、漆芸の加飾技法である蒔絵の一種で、器面の文様を立体的に盛り上げて表現する技法です。技法の工程:まず、文様となる部分に錆漆(さびうるし。漆に砥の粉や粘土などを混ぜたもの)や木炭の粉などを厚く塗り重ねて、盛り上げの土台... -

平蒔絵
平蒔絵(ひらまきえ)は、漆芸の加飾技法である蒔絵の基本的な技法の一つです。その名の通り、文様を平面に仕上げることに特徴があります。技法の工程:まず、文様となる部分に漆で絵を描きます(これを描起しといいます)。漆が乾ききらないうちに、金粉や... -

津軽塗
津軽塗は、青森県弘前市を中心に伝わる伝統的な漆器で、約300年以上の歴史を持ちます。藩政時代に武士の刀の鞘の装飾として始まり、その堅牢さと独特の装飾性から「津軽のバカ塗り」の異名を持ちます。最大の特徴は、「研ぎ出し変わり塗り」という技法です... -

越前漆器
越前漆器は、福井県鯖江市河和田地区を中心に作られる、約1500年の歴史を持つ日本最古級の漆器産地です。起源は6世紀、継体天皇に黒塗りの椀が献上されたことに遡ります。最大の特徴は、「堅牢さ」と「花塗(はなぬり)」と呼ばれる塗りの技法です。花塗は... -

紀州漆器
紀州漆器は、和歌山県海南市の黒江地区を中心に生産され、「黒江塗」とも呼ばれます。室町時代に近江系の木地師が紀州材を用いて渋地椀を作ったのが起源とされ、江戸時代には紀州徳川藩の保護のもと発展しました。最大の特徴は、実用性の高さと「根来塗(... -

会津塗
会津塗(あいづぬり)は、福島県会津地方で室町時代から発展した伝統工芸品です。安土桃山時代に蒲生氏郷(がもううじさと)が日野(滋賀)から職人を招き、産業として確立しました。最大の特徴は、「縁起の良い意匠と多彩な加飾」です。松竹梅や破魔矢を... -

山中漆器
山中漆器は、石川県加賀市の山中温泉地区に伝わる漆器です。安土桃山時代に木地師が移住したのが始まりとされ、轆轤(ろくろ)を用いた挽物(ひきもの)技術が日本一と称されるほど発達しています。最大の特徴は、木地の表面に平行で極細の筋を入れる「加... -

金沢漆器
金沢漆器は、石川県金沢市を中心に作られる漆器で、加賀藩の保護のもと、武家文化の力強さと貴族文化の優美さが融合し発展しました。最大の特徴は、「加賀蒔絵」と呼ばれる高度な加飾技術です。平蒔絵、高蒔絵、研出蒔絵といった多様な技法に加え、螺鈿(... -

輪島塗
輪島塗は、石川県輪島市で生産される日本を代表する高級漆器です。最大の特徴は、下地工程で輪島産の珪藻土を焼成した「地の粉(じのこ)」を漆に混ぜて塗る「本堅地(ほんかたじ)の技法」にあります。これにより、非常に堅牢で丈夫になり、破損しても修... -

山本晃
山本晃は、山口県光市出身の彫金家・金工作家(1944-2024)です。東京デザイナー学院でデザインを学んだ後、奥山峰石や増田三男といった人間国宝から助言を受けつつ、ほぼ独学で彫金技術を習得した異色の経歴を持ちます。彼は、金属板をデザインに合わせて... -

増田三男
増田三男は、埼玉県の浦和(現さいたま市)出身の彫金家(1909-2009)です。東京美術学校(現・東京藝術大学)で清水南山や海野清に師事し、伝統的な金工技術を習得しました。卒業後、富本憲吉を生涯の師と仰ぎ、「模様から模様をつくるべからず」という富... -

中川衛
中川衛は、石川県金沢市を拠点に活動する金工作家・彫金家(1947年-)です。金沢美術工芸大学で工業デザインを学び、卒業後は松下電工(現パナソニック)で工業デザイナーとして働いたという異色の経歴を持ちます。27歳で帰郷後、加賀象嵌の美しさに触れ、... -

内藤四郎
内藤四郎は、昭和時代に活躍した東京都出身の彫金家(1907-1988)です。東京美術学校(現・東京藝術大学)で清水南山や海野清に師事し、彫金技術を習得しました。特に、蹴彫(けりぼり)や平脱(へいだつ)といった伝統的な技法を得意とし、その技術を駆使... -

鴨下春明
鴨下春明は、明治末期から平成時代にかけて活躍した彫金家(1915-2001)です。高等小学校卒業後、伯父で彫金家の桂光春(かつら みつはる)に師事し、江戸金工の流れをくむ伝統的な彫金技法を習得しました。戦後の工芸展で、刀装具として発達した彫金技術... -

金森映井智
金森映井智は、富山県高岡市出身の彫金家・金工作家(1908-2001)です。富山県立高岡工芸学校で金工全般を学び、高岡彫金の名工・内島市平に師事しました。伝統的な布目象嵌(ぬのめぞうがん)の技法を得意とし、この技法に独自の幾何学模様やモダンな意匠... -

鹿島一谷
鹿島一谷は、明治から平成時代にかけて活躍した日本の彫金家(1898-1996)です。代々金工を家業とする家に生まれ、祖父から家伝の布目象嵌(ぬのめぞうがん)の技法を学びました。布目象嵌とは、地金に布目状の刻みを入れ、そこに他の金属を打ち込む象嵌技... -

海野清
海野清は、明治から昭和時代にかけて活躍した日本の彫金家(1884-1956)です。帝室技芸員であった父・海野勝珉に師事し、水戸彫の伝統的な彫金技法を継承しました。また、東京美術学校(現・東京藝術大学)を卒業後、同校の教授を務め、フランスへの留学も... -

天像
「天像(てんぞう)」とは、仏教の護法神である「天部」をかたどった像です。特に密教で重要な「十二天」は、八方位(八方天)と天・地・日・月の計12尊からなり、方位の守護や密教の修法に用いられました。代表的なものに「薬師寺吉祥天像」などがありま... -

明王像
明王は、仏像の階層の中で、如来の化身(真理を説くための変化した姿)と位置づけられる尊格です。仏の教えに従わない衆生(人々)を力ずくで導き、煩悩を打ち砕くという重要な役割を担っています。明王像の最大の特徴は、恐ろしい形相(忿怒相:ふんぬそ... -

菩薩像
菩薩は、仏教において悟りを開いた如来に次ぐ位にあり、自身も修行しつつ、全ての人々(衆生)を救済する慈悲の精神を持つ尊格です。菩薩像の姿は、悟りを開く前の釈迦(インドの王子)がモデルとなっており、最高の悟りを開いた如来像とは対照的に、豪華... -

如来像
如来は仏像の階層の中で最も尊い位にあり、「真理を悟った者」「悟りの世界から来た者」を意味します。如来像は、最高の悟りを開いた釈迦(しゃか)の姿を規範とし、質素で飾り気のない姿で表されるのが最大の特徴です。―主な特徴― 髪型: 髪を小さく丸めて... -

仏像
仏像は、仏教において信仰の対象として造られた、仏や菩薩、明王、天部などの姿を形に表した彫刻です。本来は教祖である釈迦(ブッダ)の姿を表現したものから始まり、やがてその教えや世界観を伝えるために、多様な姿が作られるようになりました。仏像は... -

テラコッタ
テラコッタは、イタリア語で「焼いた土」を意味し、粘土を成形し釉薬(うわぐすり)をかけずに比較的低温(700~800℃程度)で焼成した素焼きの陶器や彫刻作品を指します。この技法の特徴は、粘土に含まれる酸化鉄が焼成によって発色し、赤褐色や茶色がかっ... -

鋳銅
鋳銅とは、青銅(ブロンズ、銅を主成分とし錫などを混ぜた合金)や真鍮(しんちゅう、銅と亜鉛の合金)などの銅合金を、溶かして型(鋳型)に流し込み、目的の形状に成形する技法、またはその製品自体を指します。彫金や鍛金と並ぶ主要な金属加工技術の一... -

象牙彫り
象牙彫りは、主に象の門歯が発達した象牙を素材とする彫刻です。象牙は、独特の乳白色(アイボリー)と、適度な硬度・粘り、そして加工のしやすさを兼ね備えており、古来より世界中で珍重されてきました。日本では奈良時代の正倉院宝物に見られるなど古く... -

木彫り
木彫りは、木材を素材として彫刻刀やノミなどの工具を用いて形や模様を彫り出す技法、またはその作品自体を指します。石や金属に比べ、温かみのある質感と、彫りやすく加工しやすいという特性を持ち、古くから世界中で用いられてきました。日本では、飛鳥... -

ブロンズ像
ブロンズ像は、主に銅を主成分とし、錫(すず)や亜鉛などを混ぜた青銅(ブロンズ)を素材とする彫刻作品です。高い硬度と耐久性を持つため、古代ギリシャ・ローマ時代から制作され、屋外のモニュメントや芸術作品に広く用いられてきました。日本の「銅像... -

アンティーク家具
アンティーク家具とは、一般に製造から100年以上経過した家具を指します。アメリカの通商関税法で定められた定義が広く知られていますが、ヨーロッパでは100年未満でもデザインの伝統を継承したものは「アンティーク」と呼ばれることがあります。―特徴と価... -

古銭
古銭(こせん)とは、現在通用していない古い貨幣の総称です。主に硬貨(コイン)や紙幣を指し、日本国内では江戸時代以前の和同開珎や寛永通宝などの銭貨、明治時代以降の旧紙幣や記念貨幣なども含まれます。海外の古いコインも古銭のコレクション対象で... -

切手
切手とは、郵便物を送る際の郵便料金の支払い済みを証明するために貼り付ける証票です。日本では1871年(明治4年)に発行が始まりました。 切手は大きく分けて以下の3種類があります。 ・普通切手: 定番の意匠で日常の郵便に使用され、常に販売されていま... -

コレクション品
コレクション品とは、個人の興味や愛好に基づき、系統立てて集められた物品の総称です。単に物を集めるだけでなく、分類、整理、鑑賞、保存といった行為を含みます。その対象は多岐にわたり、先の回答で触れた骨董品、美術品、宝飾品、時計といった高価な... -

時計
時計は、時を計測・表示するための機器です。設置場所で分類されるクロック(置時計・掛時計など)と、携帯できるウォッチ(腕時計・懐中時計など)に大別されます。主な駆動方式時計の心臓部であるムーブメントは、大きく以下の2種類に分かれます。1.機械... -

ブランド品
ブランド品とは、特定の企業やデザイナーによって製造・販売され、高い認知度と信用力を持つ製品の総称です。特に「ハイブランド」や「ラグジュアリーブランド」と呼ばれるものは、一般的な製品と一線を画します。高品質な素材と職人技: 最高級の素材が選... -

宝石
宝石とは、「美しい」「希少性が高い」「耐久性がある」という3つの条件を兼ね備えた固形物の総称です。その多くは鉱物ですが、真珠や琥珀、サンゴのように生物由来の有機物も含まれます。種類と分類宝石は、特に価値の高い貴石と、それ以外の半貴石に分類... -

貴金属
宝飾品(ジュエリー)の主素材として用いられる貴金属は、金(ゴールド)、プラチナ(白金)、銀(シルバー)の3種類が代表的です。これらは化学的に安定しており、変色・腐食しにくいという特性から、美しさを長く保つことができます。金(Gold / Au): ... -

美術品
美術品とは、美術的な価値や美的な鑑賞を主な目的として制作された芸術作品の総称です。視覚を通じて感動や思考を促す「造形芸術」を指し、文芸や音楽などの他の芸術分野と区別されます。主なジャンルは、絵画(油彩、日本画など)、彫刻、版画が挙げられ... -

骨董品
骨董品(こっとうひん)とは、希少価値や美術的・歴史的価値のある古美術品や古道具類の総称です。一般的に、作られてから100年以上が経過したものを指すことが多いですが、日本においては明確な定義はなく、昭和期の古いものなども含まれることがあります... -

丹波焼
丹波焼(または丹波立杭焼)は、兵庫県丹波篠山市今田町立杭地区で焼かれる陶器で、日本六古窯の一つに数えられます。その歴史は平安時代末期から鎌倉時代初期に遡り、800年以上にわたり生活用器を中心に作られてきました。最大の特徴は、桃山時代以降に導... -

信楽焼
信楽焼は、滋賀県甲賀市信楽町を中心に、約1260年の歴史を持つ日本六古窯(にほんろっこよう)の一つです。特に鎌倉時代以降、茶の湯の発展とともに茶道具として重宝され、広く知られるようになりました。最大の特徴は、良質な信楽の土が生み出す素朴で暖... -

京焼
京焼とは、京都で生産される陶磁器の総称です。特に清水寺の参道で作られていた清水焼が代表的で、現在では京焼・清水焼として知られています。都として栄えた京都で、公家や茶人の嗜好品として発達したため、特定の様式にこだわらず、各地の優れた技術や... -

常滑焼
常滑焼(とこなめやき)は、愛知県常滑市を中心に知多半島で焼かれる炻器(せっき)で、日本六古窯の一つに数えられます。その起源は平安時代末期にさかのぼる、長い歴史を持つ焼き物です。初期の特徴: 古代から大甕(おおがめ)や壺などの大型の日用雑器... -

瀬戸焼
瀬戸焼(せとやき)は、愛知県瀬戸市周辺で生産される陶磁器の総称で、日本六古窯の一つです。その歴史は1000年以上と古く、古くから焼き物といえば「せともの」と呼ばれるほど、日本の陶磁器の代名詞的存在でした。歴史: 平安時代末期に施釉陶器(ゆうや... -

萩焼
萩焼(はぎやき)は、山口県萩市一帯で作られる伝統的な陶器です。豊臣秀吉の朝鮮出兵の際に朝鮮から連れてこられた陶工が開窯したのが始まりで、茶陶(茶の湯の道具)として特に高い評価を受けてきました。素朴な土の風合い: ざっくりとした焼き締まりの...