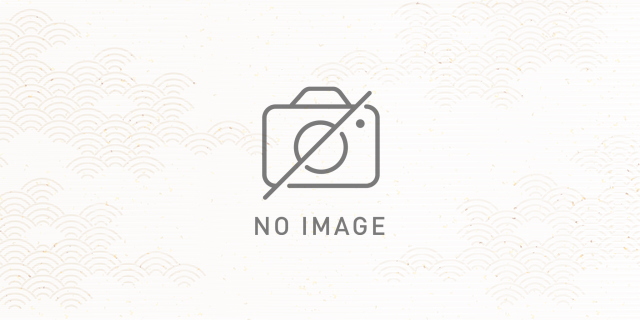日本最後の文人画家として知られる「富岡鉄斎(とみおかてっさい)」といえば、誰でも一度は耳にしたことのある有名人なのではないでしょうか。主に明治時代・大正に活躍した人物になります。生涯文人としての人生を貫き、世界中からも高い評価を得ています。
京都で法衣商十一屋伝兵衛富岡維叙の次男として誕生します。もともと幼い頃より少し耳が不自由だったものの、勉学に励んできました。石門心学や国学・勤王思想・漢学・詩文・陽明学など幅広い分野を学び、18歳の頃に南北合派の窪田雪鷹、大角南耕に絵について手ほどきを受けます。
文久2年に山中静逸と出会ったことをきっかけに絵を描き生計を立て始めるようになります。維新後の30代~40代まで神官を勤め日本各地を旅してきました。北海道を旅した際に、アイヌの風俗に触れ代表作も生み出しています。
教育者としても活躍し、私塾の立命館では教員も経験しています。89歳で亡くなるまで数多くの作品を残しています。歳を重ねてから評価されるなど晩年に活躍した人物でもあります。また色彩感覚に優れた人物としても知られ、多彩な色使いも特徴の一つです。
・富岡鉄斎の代表作とは
・華之世界図
富岡鉄斎は日本各地を訪れた画家でもあります。大正3年に描かれたこちらの作品は、奈良県の吉野の桜を描いたものとしても知られています。古来より多くの人に愛された奈良の名所を、富岡鉄斎がどのように見ていたのかがわかる作品でもあります。山の頂から下りてくる道や桜の木々とのコントラストが美しい作品です。
・扇面新居雅会図
富岡鉄斎は晩年、文芸界の重鎮として活躍していました。京都で多くの交流を示す作品としても知られているものになり、文華苑に咲き誇る季節の美しい花々を描いたものになります。木々の荒々しさも感じつつ、美しく咲き誇る花々が印象的ですね。描かれているのは梅の花になり、冬から春にかけての季節を描いたものなのでしょうか。
・安倍仲麻呂明州望月/円通大師呉門隠棲
安倍仲麻呂が、明州で別れの宴を催した際に月を見て故郷を思い出します。そこで有名な「天の原」の歌を詠んだ故事を描いたものです。79歳のときに作った作品になり、色彩感覚の美しさを感じさせますね。
・まとめ
富岡鉄斎の作品の多くが、日本の昔から変わらぬ風景を描いたものも多くどこか懐かしく温かい気持ちにさせてくれますね。日本で最後の文人画家として高く評価されているのも納得できる作品ばかりです。勉強熱心で多彩な書画作品を生み出してきたこともあり、他の画家とは一味違う作品ばかりです。