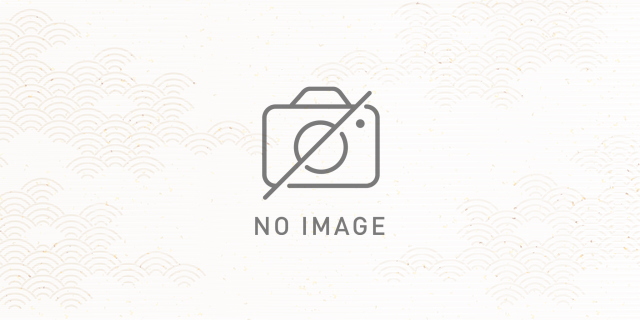生涯が謎に包まれた人物でもあり、絵師として確かな実績を残し続けた「俵屋宗達」を知っていますか?町人だったこともあり生没年不詳であること、絵師として大出世した人物でもあります。俵屋宗達の作品を見ると「あ、これ知ってる!」と思うものも多く、いかに実力のある人物だったのかがわかると思います。
俵屋宗達という名前は、金銀泥の下絵や扇絵などを製作販売する「俵屋」を営んでいたことに由来します。自宅で商売をし茶会を開いていた記録もあることから、比較的裕福な家庭で生まれ育ったのではといわれています。
本阿弥光悦の引き立て役としと名前を残したこと、日本美術に数多くの作品を輩出しその実績が高く評価されています。俵屋宗達の作品は高く評価され、琳派の尾形光琳が手本にしたことでも知られています。実際に二人の活動していた時期は100年以上の隔たりはありものの、尾形光琳が何度も模写して、たらしこみなどの技法を学び取っていたともいわれています。
60歳を過ぎた頃、朝廷から僧侶の位階である「法橋」に叙せられました。これは町人としては異例の出世でした。
■俵屋宗達の代表作は
1. 舞楽図屏風
珠玉の傑作としても知られる作品になり、重要文化財に指定されています。京都の第五時に伝わる2曲1双で制作されたものです。5つの有名な舞楽演目を描いた作品になり、左側には大空を飛ぶ鶴を表現した「崑崙八仙」を舞っている、緑装束の4人もいます。
シンプルな構図に見えるかもしれませんが、実はとても奥深く見どころも多い作品です。6曲1双が屏風画に2曲1双にされている点も、斬新性のあるものといえます。
2. 風神雷神図屏風
誰もが一度は目にしたことのある風神雷神図屏風は、国宝にも指定される代表作になります。もともとは、17世紀初頭に京都の豪商「ウツダキンノリ」によって依頼され制作したものになります。金箔が一面に貼られていること、黒雲にのり風を操りながら舞い降りる風神の姿や、力強く雷太鼓を打ち鳴らす雷神の姿を描いています。この作品に関しての文献は一切残されていないものの、ひと目見たら忘れない見事な作品になっています。
・まとめ
俵屋宗達の作品は、どれも素晴らしいものばかり!尾形光琳が熱心に模写したといわれるのも納得できますね。謎多き絵師でもあり、高い技術を誇る人物です。