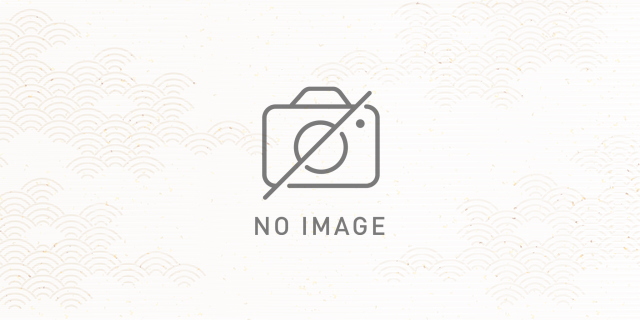江戸時代後期に活躍した南画家でもあり、日本の各地を描いた人物といえば「田能村竹田(たのむらちくでん)」ではないでしょうか。代表作も数しれず、なかには重要文化財に指定されているものもあります。
現在の竹田市の岡藩藩医の家で生まれたものの、武士のなかでは低い身分にあり生活はとても厳しい家庭で育ちました。6歳で素読をはじめ、11歳で藩校由学館に入学するもその成績の優秀さもあり唐橋君山より、同人に迎えられます。
医業の道に進むも合わず22歳のときに由学館に出仕してしたうえで儒員になります。27歳で家督を相続するものの、1811年に藩内に百姓一揆が起こります。何度も健言書を藩に提出したもののいずれも受け入れられることはなく、辞職の道を進むことになります。
その後、日本各地を旅しながら20歳の頃より谷文晁に学び南宗画を描き、忠実で品質高いものを世に送り出しています。長崎派の画家より、中国絵画の技法を学んだこともあるのだとか。交友関係も幅広く弟子には有名な高橋草坪や帆足杏雨などがおり、59歳で亡くなるまで多くの著作を残しています。
・田能村竹田の代表作とは
・梅花書屋図
画面の中央部分には石積みの塀に囲まれた大きなお屋敷が見えます。書斎のなかには男性が二人楽しげに笑い合っているのが印象的ですね。寒い冬から徐々に春へと季節の変わる梅の時期を描いたものになります。樹木の高低差などを描きながら奥行きのあル壮大な景色を描いたものを表現しています。
・松巒古寺図
頼山陽との親交を裏付けるものとして知られている作品です。大胆に描かれた斜面や木々がとても迫力のある一枚です。頼山陽の依頼を受けて描いたものの、上京の際に持っていくとすでに亡くなってしまっていたため寄贈されたといわれています。細部まで細かく描かれ、奥深さを感じせますね。
・月下芦雁図屏風
屏風に堂々と描かれる夜空を舞う鳥の姿が描かれたものになります。シンプルな構図ではあるものの、雲の加減や陰影がとても美しい幻想的な作品になります。鳥の動きも生き生きとしていて、実際に目の前で見ているかのような錯覚に陥ってしまいそうです。
まとめ
田能村竹田が残した作品の多くが重要文化財に指定されているものの、資料も少ないので知らない人もいるかもしれません。どの作品も構図がとても美しく、いつまでも眺めていたくなるような魅力的な作品ばかりです。旅を通していろいろな景色を眺めてきたからこそ、描けたものなのではないでしょうか。