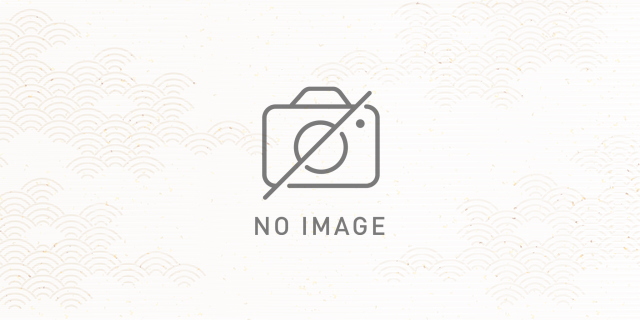本来の俳句の形に縛られることなく自由律俳句の代表者としても知られる「種田山頭火(たねださんとうか)」は、多くの人に愛されました。実際に国内に句碑が500基以上残されており、58年の短い人生のなかでたくさんの功績を残した人物でもあります。
1882年に山口県の佐波郡にで大地主の種田家の長男として生まれます。5人兄弟で育つも。10歳のときに父親の芸者遊びなどが原因となり、母親は井戸に投身自殺をしてしまいます。
そのため、祖母のツルによって育てられ、種田山頭火の放浪者のきっかけになったできごととしても語り継がれています。その後父が所有していた酒造場を継ぎますが、経営に失敗し、住んでいた家屋まで手放すことになりました。
31歳のときに「層雲」にてはじめて俳句が投稿され、俳句選者として高く評価されるまでになります。50歳のときに自殺未遂を起こし、54歳のときに山梨県から長野県まで歩き、数々の作品を生み出しました。その後も東北地方を旅しつつ、愛媛県の松山市に移住し「一草庵」をを結びました。
・種田山頭火の代表作とは
・あるけばかつこういそげばかつこう
歩く道の途中でかっこうが鳴いていて、急いで進むもまたかっこうが鳴いていたことを表現したものになります。初夏の山野を一人で進んでいく様子を表した俳句なのではといわれています。無季俳句としても知られている一句になります。
・気まぐれの 旅暮れて桜 月夜なる
種田山頭火の俳句のなかでも比較的定型に近いものです。目的もないまま気の赴くままに旅をしている様子を表現しています。旅をたくさんしていたからこそ生まれた俳句です。今日も日が暮れて、春ならではの夜桜の美しさが伝わってきますね。
・ふるさとは あの山なみの 雪のかがやく
ふるさとは向こうに見える山並みのように、雪が輝いているのではないだろうかという風景を表現した俳句になります。ふるさとに対してのどこか懐かしく寂しい風景が浮かんできます。ただ種田山頭火にとってふるさとにはさまざまな想いがあったはずです。こうであって欲しいという幻想を表現したともいわれています。
まとめ
種田山頭火の俳句はどれもその風景を思い起こしてくれるものばかりです。日本の四季があるからの景色を旅を通して感じ、ときには寂しくも思い歌っていたのかもしれません。自由俳句を生み出した人物でもあり、旅やお酒をこよなく愛した人物でもあります。俳句をより身近に感じさせてくれるのはさすがです。