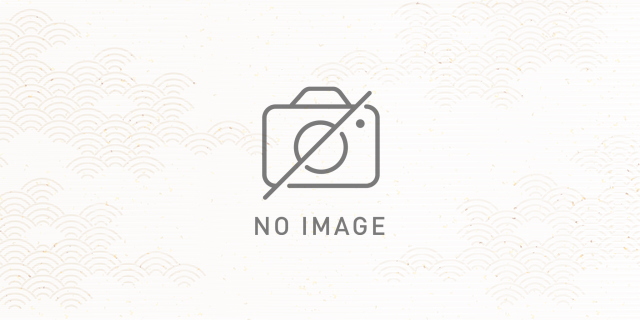明治・大正・昭和の3代に渡って活躍した、小説家であり俳人として有名な「高浜虚子(たかはまきょし)」をご存知でしょうか。雑誌の「ホトトギス」の発行に尽力したことでも知られ、世界で活躍する多くの俳人を育てた人物でもあります。
愛媛県の温泉郡長町新町に生まれ、父親の池内政忠は元松山藩の藩士として活躍した人物です。祖母の実家である“高浜姓”を継ぎ、自分の子どもである次男に池内の名前を名乗らせました。中学生時代に1歳年上の河東碧梧桐と同級生になり、紹介で正岡子規から俳句を教わるようになります。
1891年には正岡子規より「虚子」の号を授かるまでになります。
日本の日刊新聞である「萬朝報」に入社したものの、母親の病気のため除籍処分になり、正岡子規の協力を得て、俳誌のホトトギスを引き継ぎ東京に移転します。
1902年には俳句の創作を辞め、小説の創作に没頭。1954年に85歳でなくなるまで多くの俳句を詠み弟子を輩出してきました。自分の信じた道をひたすらに突き進むような性格だったともいわれています。
・高浜虚子の代表作
高浜虚子の俳句は五七五調で詠まれるべきであると唱え、季語を重んじたものになります。伝統的な俳句を守り、自然そのままの美しさを表現したものばかりです。
・濡縁にいづくとも無き落花かな
濡縁にどこからともなく桜の花びらが落ちてきたものの、周囲に桜の木は見当たらない。どこから来たのであろう。高浜虚子の俳句には桜を季題として使用したものが多く、500種類以上ある俳句のなかでも20句前後を占めるといいます。桜の花びらに対しての愛着を感じさせる美しい俳句です。
・虹立ちて雨逃げて行く広野かな
昭和8年5月に開催された「丸之内倶楽部俳句会」で詠まれた一句です。広い野原に激しい雨が降っていたものの、それが次第に遠のき日差しが入り美しい二次がかかったことを俳句として表現しています。雨逃げていくと擬人化したのも遊び心がありますね。
・大空にのび傾ける冬木かな
冬の大空に寂しい、活気のない条件のなかに決然と立っている冬木の様子がよく取られられた俳句でもあります。静寂のなかに美しさを見いだせる作品でもあり、冬の訪れを実感させてくれる俳句といえるのではないでしょうか。
まとめ
人生のなかで500句以上の俳句を詠み続けた高浜虚子。どれも五七五の短い歌のなかにその季節の美しさや魅力を感じさせてくれるものばかりです。俳句ならではの奥深い世界を実感できるのではないでしょうか。