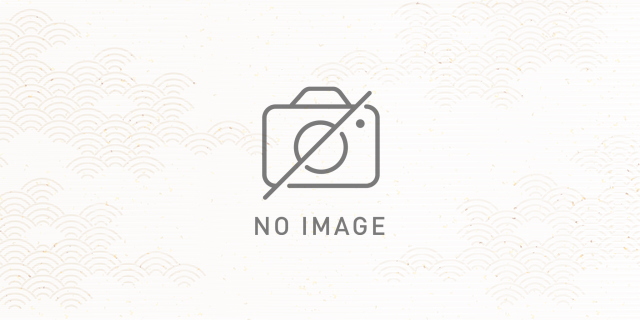日本画家の「木村武山」といえば、明治時代から昭和初期に活躍した人物です。幼い頃から絵を描く才能に恵まれていたともいわれていますが、実業家であった父親の影響も強く受けています。
「日本を代表するカラリスト」とも称されるほどの色彩豊かな作風が特徴のある人物としても知られています。多岐にわたる作品を次々に生み出した木村武山の魅力を詳しく紹介していきたいと思います。
木村武山は、茨城県の笠間市に生まれ木村信義の長男としてこの世に誕生しました。物心が付く前から絵に親しみ、若干12歳という若さで「武山」の称号を受けるまでになります。
明治24年に東京美術学校に入学すると「日本美術院」に参加します。6年後には茨城県北茨城市に一家をあげて同行し、たくさんの作品を制作し続けました。画業の主流になった「仏画」も並行して描き始め、日本美術院の中心的存在としても経営に尽力しました。
昭和12年には脳内出血で倒れてしまい、笠間で静養するも右手の自由が利かなくなり左手で描くようになると「左武山」の異名を取るようになります。昭和17年に喘息のため亡くなりました。
■木村武山の代表作とは
1. 祗王祗女
平清盛の若い愛人であった白拍子を描いた作品になり。祇王は、仏御前と呼ばれる16歳の若い女性が現れるとあっさり捨てられてしまい、母親と妹の祇女と一緒に髪を剃り嵯峨の奥深くにこもってしまいました。
その後負い目を感じていた仏御前は同じように髪を剃り庵にやってきて一緒に生活したそうです。そんな祇王の人生を匠に描いた本作は、何もないシンプルな背景とそこに立ちすくむ祇王の姿を描いたものになります。
どこかさみしげでいつまでも眺めていたくなるような作品です。
2. 伊邪那岐・伊邪那美命
1904年~1906年に描かれた作品になり兄弟夫婦神でもある「イザナミノミコト」と「イザナギノミコト」を描いたものになります。この二人によって日本の国土が造られました。たくさんの子供達に恵まれるも、火の子を出産するときに大やけどをおい負傷したことで亡くなります。雲の上から日本を眺めているのでしょうか。シンプルでほとんど色彩を使っていないものながら、細部にまでこだわりぬいてつくられた作品なのが伝わってきますね。
・まとめ
木村武山の作品は、どれも神聖な雰囲気すら感じさせるものばかりです。たくさんの作品を残し続け、色彩の美しさにも定評があります。木村武山がどうしてここまで高く評価されたのか、作品を見れば必ず納得できるはずですよ。