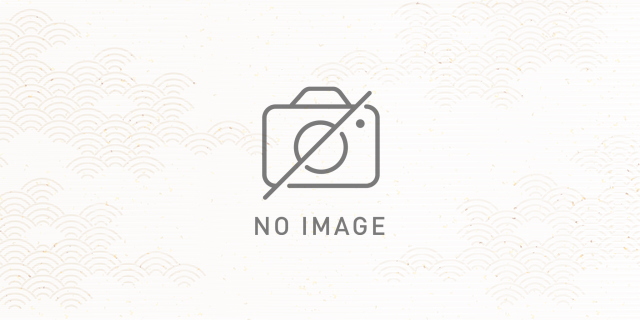茶道具– category –
-

茶器
茶道具とは、茶の湯(抹茶)や煎茶の席で用いられる全ての器具の総称です。その中でも、特にお茶を点てたり、直接関わる道具を茶器と呼びます。抹茶の茶器の代表は、茶を入れておく茶入(濃茶用)や棗(なつめ・薄茶用)です。これに、抹茶を飲むための茶... -

茶掛
「茶掛(ちゃがけ)」とは、茶室の床の間(とこのま)に掛ける掛け軸のことで、茶道具の中で最も格が高く、重要とされる道具です。単に「軸」とも呼ばれます。茶掛は、その日の茶会の主題(テーマ)や亭主(主人)の客人へのメッセージを伝える役割を担っ... -

香炉
茶道において、香りを焚く道具には「香合(こうごう)」が中心的に用いられ、香炉(こうろ)は主に仏事や香道で使われますが、広い意味での茶道具・茶室のしつらえとして用いられることもあります。茶席の正式な流れでは、お湯を沸かす炭を継ぐ際に、香合... -

花入
「花入(はないれ)」は、茶室の床の間(とこのま)などに飾る花を入れる容器で、茶の湯における重要な装飾道具の一つです。花入は、茶会の趣向や季節感を表現する役割を持ち、掛物(かけもの)とともに客をもてなす空間の雰囲気を決定づけます。その種類... -

蓋置
「蓋置(ふたおき)」は、茶道で茶釜の蓋や、湯を汲む柄杓(ひしゃく)の合(ごう:水をすくう部分)を一時的に置くために用いられる、小さな台です。炉(ろ)や風炉(ふろ)のそばに置かれ、点前(おてまえ)を円滑に進めるための重要な役割を果たします... -

香合
「香合(こうごう)」は、茶道における香(こう)を入れておくための小さな蓋付きの容器で、茶道具の一つです。主に、炭手前(すみまえ)で、湯を沸かす炭に火を移す際にくべる香木や練香(ねりこう)を収納する役割があります。この香をたくことで、茶室... -

鉄瓶
「鉄瓶(てつびん)」は、鉄製の湯沸かしで、茶道で湯を沸かす「茶釜(ちゃがま)」を小型化し、注ぎ口と持ち手(鉉:つる)を付けたものです。江戸時代後期に、茶釜よりも手軽に使える道具として誕生しました。茶道においては、正式な席で使われる茶釜に... -

風炉
「風炉(ふろ)」は、茶道で茶釜(ちゃがま)をかけてお湯を沸かすために用いる道具です。通常、畳を切った「炉(ろ)」を用いる寒い季節(晩秋から春)に対して、初夏から秋の時期(5月〜10月頃)に使用されます。客の座から火元を離すことで、見た目にも... -

茶釜
「茶釜(ちゃがま)」は、茶の湯(茶道)において、抹茶を点てるためのお湯を沸かすために用いられる、最も重要な茶道具の一つです。主に鉄で作られており、火にかける場所によって名称が変わります。畳を切って作った「炉(ろ)」に据えるものが一般的で... -

棗
「棗(なつめ)」は、主に茶道で抹茶を入れるのに使う茶器の一種です。木製の漆塗り(うるしぬり)でできた蓋付きの容器で、特に薄茶(うすちゃ)を入れる「薄茶器(うすちゃき)」の代表的な形として広く知られています。その名前は、形が植物のナツメの... -

水指
水指(みずさし)は、茶席において「清らかな水」を貯えておくための容器です。茶を点てる際に、釜へ水を補給したり、茶碗や茶筅を清めたりする水として用いられます。単なる実用品に留まらず、茶室の床の間や棚に置かれることで、空間の景色を構成する重... -

茶杓
茶杓(ちゃしゃく)は、茶入から抹茶をすくい取り、茶碗に入れるための細長い匙(さじ)です。竹を削って作られるものが主流であり、その一本の竹の中に「侘び寂び」の美意識と茶人の心が凝縮されています。素材と形状: かつては象牙などが用いられました... -

茶入
茶入(ちゃいれ)は、茶道で濃茶の抹茶を入れておくための陶磁器製の容器です。漆器の棗(なつめ)が主に薄茶用であるのに対し、茶入は濃茶の席で使われ、その歴史的背景から茶道具の中でも特に格式高いものとして重んじられてきました。室町時代から戦国... -

茶筅
茶筅(ちゃせん)は、抹茶とお湯を均一に混ぜ合わせ、きめ細かな泡を立てるために不可欠な竹製の道具です。茶道のために特化して作られた機能美を持つ道具であり、茶の湯の風味を左右します。役割と構造: 主な役割は抹茶を攪拌すること。一本の竹を細かく... -

茶碗
茶碗は、茶道において抹茶を点て、客に供する最も重要な主役となる道具です。単なる器ではなく、亭主の趣向や「侘び寂び」の美意識を表現する鑑賞の対象とされます。産地により唐物(中国製)・高麗物(朝鮮半島製)・和物(日本製)に大別されます。特に... -

茶道具
茶道具は、茶道における「侘び寂び」の精神と美意識を体現する道具一式で、単なる実用品以上の芸術品として重要視されます。茶会では、亭主の心遣いや趣向を客に伝える役割を担います。抹茶とともに中国から伝来した当初は豪華な唐物が中心でしたが、千利... -

青木木米
江戸の後期に活躍した、京都出身の陶芸「京焼」や絵師として有名な人物です。なかでも煎茶器に優れていたこともあり、京焼の幕末三名人と称されました。もともとは裕福な家で生まれ育ちましたが、陶説(書籍)を読み、感銘を受けたことで、陶芸を作る道を... -

荒川豊蔵
人間国宝としても名高い人物でもあり、昭和を代表する美濃焼で有名になった人物です。出身は岐阜県の多治見市になり、兵庫、名古屋へと拠点を移し生活しました。星岡窯にいたときに、美濃焼の美しさに惹かれ、いつかは自分の手で作ることを決意します。家... -

飯塚小玕斎
東京の本郷区で生まれ、東京の美術学校を卒業します。その後、戦争のため入隊し出征、疎開先の栃木県にある高等女学校にて約10年間講師を務めます。竹工芸家として従事した経験から、人間国宝として認められるようになりました。北斗賞や菊花賞を受賞する... -

飯塚琅玕斎
栃木県出身の竹工芸家として知られた人物です。父親より技術を学び成功な技法や、独創的な世界観、斬新なデザインなどもあり有名になりました。竹細工といえば、日常生活で使うものでしたが、それを芸術として引き上げた人物でもあります。その技術力の高... -

板谷波山
茨城県出身、明治~昭和にかけて活躍した陶芸家として知られています。茨城県の名誉県民でもあり、文化勲章受章者です。東京美術学校で基礎を学び、石川県の工業学校の主任教諭として採用され、これをきっかけに陶芸の世界に打ち込み始めます。貧しい生活... -

井上萬二
佐賀県の有田町で生まれ、有田焼を世に広めた重要な役割を担った人物です。日本工芸会参与としても認定あされ、人間国宝としても知られています。生家が窯元だったものの、一時は海軍の飛行予防練習生となります。父親の勧めもあり、酒井田柿右衛門窯に務... -

今泉今右衛門
佐賀県の陶芸家でもあり、江戸時代からの伝統を今に守り続けている人物です。鍋島焼は、一子相伝の技法としても知られており、今は14代目が引き継いでいます。色鍋島と呼ばれる品格のある美しい色彩や、赤の調合が特徴でもあり深いこだわりを感じます。現... -

大樋長左衛門
石川県金沢市出身の陶芸家になり、大樋焼の当主として君臨しています。大樋焼の個展を開くときはその名を使いますが、自由に個展を開いて楽しみたいときは、大樋年朗の名前を名乗っていたそうです。文化勲章を受賞するなど、技術力の高さにも定評がありま... -

奥田頴川
江戸時代中期に誕生した陶芸家としても知られ、清の侵略のときに亡命した人物の末裔ではないかと考えられています。質屋を継ぐも、文化活動に熱心な人物でもあり陶芸に熱を上げていたのだとか。京焼では初めての磁器焼成に成功するなど、京焼を広めた人物... -

音丸耕堂
香川県高松市生まれの漆芸家でもあり、革命を起こした人物としても知られています。昭和17年に彫漆技術を用い出店した文展で特選を受賞します。当時は、色漆を何度も重ねて、今どきの流行りを取り入れた独特の作風からも注目されるようになります。重要無... -

加藤唐九郎
愛知県の春日井市出身の陶芸家であり、明治から昭和にかけて活躍しました。両親が窯業を営んでいたこともあり、幼少期より自然と馴染み、のちに父親の製陶工場の一部を譲り受けるまでになります。一時期、助成の措置を講ずべき無形文化財として認定される... -

河井寛次郎
島根県出身の陶芸家でもあり、随筆や書物、詩などの幅広い分野で活躍した人物です。もともとは大工の家出身になりますが、師匠と呼べる人物はおらず学校で教育を受けた珍しい陶芸家としても知られています。1万種以上にもなる釉薬の研究、中国陶器の研究な... -

川上不白
和歌山県の家臣の家で生まれ、16歳のときに表千家七世如心斎天然宗左の内弟子となります。江戸千家の流祖としても知られる人物になり、32歳のときに江戸に茶の文化を広げたいと下り、駿河台に門戸を開きます。もともとの茶風に囚われることなく、新しい茶... -

川喜田半泥子
大阪府で生まれ、伊勢の豪商の裕福な家庭で育ちます。ただ、1歳のときに祖父や父を亡くしたため1歳で当主となります。母も18歳で未亡人になったことで実家に帰り、祖母のもとで育てられることになります。百五銀行の取締役に就任し、他の銀行を買収し規模... -

北大路魯山人
京都府出身の陶芸家でもあり、もともと士族の家柄でした。ただ、位が低かったこともあり、生活は裕福なものとはいえませんでした。義理母からの虐待もあり、近所の人が養子話を持ちかけ、福田房次郎として生きることになります。住み込みで奉公に出た際に... -

黒田正玄
千家十職に数えられる役割の一つになり、先祖代々が襲名して受け継がれてきました。茶道具をメインに製作しており、千家に伝わる由緒正しき家系でもあります。現在は十三代まで続いています。初代は天正6年に越前にて誕生しました。関ケ原の合戦の後に浪人... -

駒澤利斎
千家十職の一人でもあり、棚や香合などを制作する「指物師」として、代々受け継がれてきた名称になります。初代の情報については殆ど残されていませんが、二代目より注文を受け、指物を製作していたと考えられています。とはいえ、当時は千家とのつながり... -

近藤悠三
陶芸家として人間国宝に指定されている人物になり、京都の清水寺下出身です。実際に祖父は、清水寺の地侍として務めていたと言われています。陶磁器の試験場にて助手として勤務したあと、窯業科学などを学びます。その後、イギリスから帰国した富本憲吉の... -

酒井田柿右衛門
佐賀県生まれの陶芸家でもあり、西部伝統工芸展に何度も初入選を果たし、有田焼の陶芸協会の会員や、日本工芸会正会員として活躍しました。数々の展覧会を開き、現在は15代目に当たります。初代の柿右衛門は、乳白色に赤の上絵を焼き付ける手法を取り入れ... -

柴田是真
越後出身の宮彫師の子供として婿養子になります。11歳のときより職人気質について学び、蒔絵についての知識や技術を身につけていきます。16歳のときは、図案に頼らない仕事をするために、四条派の絵の技術も身につけています。当時、まだ活躍していなかっ... -

清水卯一
京都府出身の陶芸家であり、もともと陶磁器の卸問屋の長男として誕生しました。父が若くして亡くなったため、家を継ぐことを目的に商業学校に入学。中退し石黒宗磨のもとで弟子として陶芸を学ぶようになります。ただ、戦争もあり自宅にろくろ場を設け作品... -

清水六兵衛
陶磁器で代々受け継がれてきた名前です。初代は、大阪府の高槻市の農家で生まれ京都にて陶業を学びました。特に茶器をメインに制作していたようで、黒楽茶碗なども制作しています。現在は8代目になり、京都出身、デビュー作でグランプリを獲得するなど優れ... -

松花堂昭乗
和泉の国境で生まれ、江戸時代の真言宗の僧侶として活躍した人物になります。文化人としても有名な人になり、陶芸はもちろん、茶道や絵画、書道などに長けていたそうです。なかでも能書家としても高く評価され、独自の松花堂流などの書風を編み出したこと... -

鈴木藏
岐阜県出身の陶芸家でもあり、重要無形文化財保持者としても高く評価されています。もともと出身地が美濃焼の産地になり、父親も陶磁器試験場の技師として活躍していました。工業高校を卒業後、陶芸部試験室の助手として働き、本格的な陶土など専門知識を... -

鈴木盛久
寛永2年に御用鋳物師となり、仏具、梵鐘の製造に携わります。南部鉄器の伝統継承者として受け継がれ、それぞれ名前とは別に鈴木盛久の名前が受け継がれています。昭和21年おり、日展に何度も入選して、岩手工芸会初の特選に選ばれるようになります。技術力... -

千家十職
千家十職とは、茶道に関わる仕事をしている人で、三千家に出入りしている人の仕事を取りまとめた尊称のようなものです。例えば、塗師もそうですし茶器を作る陶芸家、指物師なども存在します。茶会は、茶室で行われ独自の作法を持っています。そのため使用... -

千宗旦
千利休の後妻連れ子だった小庵の子供として生まれました。10歳のときに家督争いを避ける目的で、利休の推薦から大徳寺に喝食として預けられるようになります。その後、千家再興が実現したことで、弟子とともに利休流のわび茶を普及させることに尽力するこ... -

千利休
戦国時代から安土桃山時代に活躍した、最も有名な茶人です。茶湯の天下三宗匠とも呼ばれるようになり、多くの弟子を抱えていたそうです。そもそも千利休の名前は、禁中茶会において、町民では参加できないことから、天皇より与えられた居士号です。千利休... -

高野松山
熊本県出身の陶芸家でもあり、蒔絵の重要無形文化財に認定されています。もともと祖父は細川藩の儒者であり、父親は校長を務めるなど由緒正しい家庭として育ちました。13歳のときに漆工科の学校に入学すると、蒔絵について強く興味を持つようになります。... -

高橋敬典
山形県出身の茶湯、陶芸家としても知られている人物です。1938年に家業を継ぐものの、1950年には弟子入りし、「和銑平丸釜地文水藻」にて初入選を果たすまでに成長します。その後、昭和天皇の山形県訪問時に釜を献上できるまでに有名な陶芸家になりました... -

高橋道八
京焼(清水焼)の窯元として代々受け継がれている名前です。特定の人だけを指すものではないので、代替わりによって多少の違いもあります。初代の高橋道八が誕生したのは、1740年の頃になり、煎茶が最も栄えた時期だったこともあり、茶器の製造に力を入れ... -

沢庵宗彭
名前からもわかるように臨済宗の僧侶であり、安土桃山時代から江戸時代にかけて活躍しました。兵庫県豊岡市で生まれ、父親は、但馬の重臣だったものの羽柴秀吉に攻められ滅亡し、浪人となります。希先西堂に師事するも亡くなり、住職を別の寺から招いたこ... -

田原陶兵衛
山口県の長門市で生まれた陶芸家です。長兄11代田原陶兵衛の跡継ぎがいなかったことで、家業を継いだとも言われています。歴代受け継がれてきた名前でもあり、茶器を中心に製造していること、高麗朝鮮陶器の研究にも朝鮮していたそうです。1956年に兄が亡... -

富本憲吉
大阪府の大地主の家に生まれ、子供の頃より絵を学べる環境で育ちます。東京美術学校に入学した際に、ウィリアム・モリスの思想に影響されロンドンに留学して卒業します。留学中に、建築家の新家孝正と出会い、写真助手として一緒に巡ります。その後、日本... -

中村宗哲
400年以上の歴史を持つ、千家十職のなかで塗り師として知られています。もともとは蒔絵を使った家具などを展開していたものの、次第に茶道具を専業とした事業展開へと変わっていきます。初代は、1617年となり独楽香合などの数々の代表作を残しています。十...
12