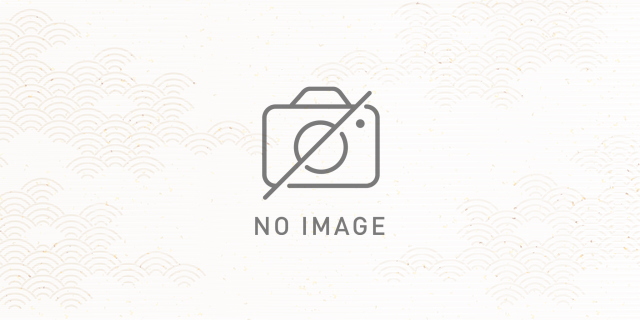作家一覧– category –
-

ジャン・ジャンセン
フランスで活躍したアルメニア人画家。デッサン力に秀で、数多くのコンクールで受賞しています。1967年以降、パリ、パームビーチ、シカゴ、東京、ヨハネスブルグ、大阪、アントニーなど、世界各地で作品を発表しています。「ベニス展」「ダンス展」「闘牛... -

杉山寧
1969年に日展常務理事。1974年に日展理事長。この間、1970年に娘婿の作家三島由紀夫が割腹自殺をして世間を騒がせます。1976年西ドイツより十字勲章を授与。1977年東京国立近代美術館評議員。1991年に東京都名誉都民。1956年から1986年12月号まで「文藝春... -

須田剋太
司馬遼太郎の「街道をゆく」の挿絵を描き、かなりの名声を得ました。力強い自由なタッチを作風とします。1906年(明治39年)埼玉県吹上町に生まれます。父親は教師でした。病弱でおとなしい子供時代を過ごし、中学卒業後、画家を志して東京美術学校を受験... -

芹沢銈介
染色工芸家として有名な人物です。静岡県静岡市葵区に生まれます。重要無形文化財「型絵染」の保持者(人間国宝)。文化功労者。静岡市名誉市民。民芸運動の提唱者である柳宗悦とともに日本各地に赴き民芸品や民具を調べました。実家の呉服商が火事で全焼... -

千住博
日本画とその技法を世界に広め、真に国際性のある芸術分野とするために、絵画、講演、執筆など幅広い活動を行っています。自然との共生を日本文化の基本理念とし創作の指針としています。1995年代表作『ウォーター・フォール』はヴェネツィア・ビエンナー... -

曽宮一念
東京都日本橋区漬町(現中央区日本橋浜町)に生まれます。本名下田喜七(しもだきしち)。大下藤次郎、藤島武二、黒田清輝に師事します。東京美術学校卒業後、山下新太郎、中村彝に手ほどきを受けます。1914年文展で褒状、1925年二科展で樗牛賞を受賞。二科会 ... -

高塚省吾
岡山市に生まれ、東京芸術大学に入学し1953年に学位を取得。在学中、梅原龍三郎、林武、硲伊之助らに師事。同年、芸大教授であり日本美術会の委員長を務めていた硲伊之助のすすめで第7回日本アンデパンダン展(日本美術会主催)に出品。その後、第1... -

竹内栖鳳
戦前に活躍した日本画家。現代日本画のパイオニア的存在。画業は半世紀にわたり戦前の京都画壇を代表する画家でした。1909年(明治42年)京都市立絵画専門学校 (現京都市立芸術大学)開校と同時に教授となり、1924年(大正13年)まで務めます。同年フランス... -

竹久夢二
魅力的な女性を描いた作品を数多く残しその詩情豊かな作品は『夢二式美人』と呼ばれました。大正ロマンを代表する人物とされ、大正の浮世絵師と称されたりもします。その他子供向けの月刊誌や、詩文の挿絵も手がけました。文筆活動も行い童謡、詩歌、童話... -

田崎広助
1917年、福岡県師範学校(現福岡教育大学)第2部卒業。在学中、坂本繁二郎、安井曾太郎に指導を受けます。関西美術院にも通いました。戦後広稜会を設立。東郷青児らと「日伯現代美術展」(伯は伯刺西爾、ブラジルの意)を開催。1949年日展審査員。その後19... -

田辺至
1886年(明治19年)12月21日東京神田に生まれます。東京美術学校で後進の指導をしながら絵画制作を続け、1926年(大正15年)第8回帝展に出品した「裸体」で帝国美術院賞を受賞します。1927年(昭和2年)明治神宮絵画館に壁画「不豫」を制作。1934年(昭和9年)... -

谷内六郎
9人兄弟の6番目として東京恵比寿に生まれます。父、久松の生家は富山県北蟹谷村(現小矢部市)にありました。駒沢尋常高等小学校卒業後、見習い工として働き、独学で絵の勉強をします。戦後、同じ漫画家の鈴木善太郎、片寄貢らと銀座の街中で政治風刺画を... -

田渕俊夫
東京都江戸川区に生まれます。1965年東京芸術大学美術学部日本画科卒業。1967年、同大学大学院日本画専攻修了。在学中、平山郁夫に師事します。1968年再興第53回日本美術院展に入選、1982年と1985年に日本美術院賞を(大観賞)受賞。その後も数々の作品で... -

鶴田一郎
専門的に絵を描き始めた頃は西洋文化の影響を受け、写実的な作品を描いていました。しかし「日本人であること」を意識するようになり、琳派や弥勒菩薩などの仏教美術、浮世絵の「美人画」「女絵」といった日本的な美意識に傾倒していきます。1987年アート... -

寺内萬治郎
洋画家寺内萬治郎は、明治42年に白馬会葵橋洋画研究会で黒田清輝に師事し、その後、東京美術学校では藤島武二に学びました。 大正7年に文展に初入選。大正11年には耳野卯三郎らと金塔社を設立します。その後、大正14年の第6回帝展に出品した『裸婦』、そし... -

東郷青児
本名東郷鉄春。彼の描く甘美で魅惑的な女性像は、書籍、雑誌、ラッピングなどに数多く使われ、昭和の時代に美しい女性を見事に描く巨匠として戦後有名になります。1957年(昭和32年)岡本太郎と日活映画「誘惑」に西郷赤児役で特別出演。日本芸術院賞も受... -

堂本印象
明治から昭和にかけて活躍した日本画家といえば「堂本印象(どうもといんしょう)」は外せません。京都に美術館も構えるなど、時代を超えて多くの人に愛されてきた人物でもあります。色彩の美しさに目を奪われてしまうような素晴らしい作品ばかりです。 18... -

三岸節子
女子美術学校(現 女子美術大学)の2年に編入しトップで卒業。1924年に三岸好太郎と結婚し、1930年に黄太郎が生まれますが1934年に夫は他界してしまいます。太平洋戦争中も疎開せず、厳しい生活の中、色鮮やかな静物画を数多く描きました。... -

棟方志功
棟方志功(むなかたしこう)といえば黒縁メガネが印象的な絵師のでもあります。青森県に記念館もあることから、一度は名前を聴いたことのある絵師なのではないでしょうか。世界の棟方とも呼ばれたように、その才能を高く評価されていたこと、書籍も数多く... -

横山大観
日本画家を代表する人物としても高く評価されているのが「横山大観(よこやまたいかん)」 です。第一回文化勲章を受賞したこと、東京都の上野に横山大観記念館もあるなど、時代を超えて愛され続けています。横山大観とはどのような人物だったのでしょうか... -

会津八一
会津八一は、新潟県で生まれ病気で体が弱かったこともあり中学生の頃より俳句に興味を持ちます。奈良旅行をきっかけに短歌にも興味を持ち「南京余唱」や「山光集」「寒燈集」などを出版します。会津八一は、美術史学の研究法なども独学でマスターするなど... -

青山杉雨
青山杉雨は、愛知県生まれで、東京の向島に上京しています。もともとは行草を得意としていましたが、戦争を挟んで古文や隷書などの研究にも熱心に取り組みます。青山杉雨は、とても読書家としても知られ、亡くなるまでたくさんの書籍を読んでいたそうです... -

芥川龍之介
芥川龍之介は、東京の京橋区出身の小説家であり、実家は牛乳製造販売業を営んでいたそうです。母親が精神的な病にかかったことで、母方の実家の芥川家に預けられ祖母に養育されます。芥川龍之介の代表作になる「羅生門」は1915年に発表したものです。1919... -

池田蕉園
池田蕉園は、東京出身の女性浮世絵師として活躍した人物であり、女性です。小学生の頃より、草双紙の絵を石版に描くなど、才能に奏でていた部分強く、慶應義塾で学業も学び、アメリカのラトガース大学に留学して鉄道を研究していた時期もあります。池田蕉... -

礒田湖龍斎
礒田湖龍斎は、江戸時代の中期に活躍した浮世絵師です。もともと江戸小川町の旗本の土屋家の浪人になり、両国の薬研堀に住居していたそうです。礒田湖龍斎は、名前が途中で変わっており、鈴木春広や湖龍斎春広などと号していた時期もあります。1776年に版... -

伊藤若冲
伊藤若冲(いとう・じゃくちゅう) 江戸時代中期の画家。京都の青物問屋(野菜の問屋)の跡継ぎとして生まれた伊藤若冲は、家業を継ぎつつも絵を描くことに熱中し、40歳になったときに家督を譲って画家としての道を歩み始めました。 専業画家になる前から、... -

伊藤博文
伊藤博文は、山口県の農家で生まれ、伊藤家に奉公をしていた経緯もあり、養子になり身分を獲得しました。その後、高杉晋作などが学んだ「松下村塾」に入門し、吉田松陰の教育を受けます。伊藤博文は、当時からとても優秀だったため、イギリス留学を経験し4... -

岩佐又兵衛
岩佐又兵衛は、江戸時代の初期に活躍した絵師です。2歳のときに、父親は織田信長に敗れ亡くなり、母親は六条河原で処刑、乳母に救われて京都で育ちます。大阪の陣の頃、福井藩主の松平忠直に招かれ、20年近く住みながら絵を描きます。その後、千代姫が嫁ぐ... -

上村松篁
上村松篁は、京都を中心に活躍した画家であり、母親(上村松園)も日本画家だったことから子供の頃から絵を描くことがとても好きな少年でした。ただ、ほとんどを二階の画室にこもっていたこともあり、二階のお母さんと呼んでいた時期もあるのだとか。自然... -

歌川国貞
歌川国貞は、江戸の後期に活躍した、浮世絵師です。本名を角田庄五郎といい、後に三代目「歌川豊国」と名乗るようになります。描く絵の特徴として、面長イノシシ首型の美人画が多く、1万点以上の作品を残したことで知られています。歌川国貞は、22歳の頃か... -

歌川国芳
歌川国芳は、美人画を描いていた絵師としては、そこまで知名度が高くないもののファンも多く傑作を残している人物です。江戸末期の浮世絵師になり、枠に留まることを知らない自由な画風も人気がありました。歌川国芳は、江戸日本橋にうまれ、幼少期から絵... -

歌川広重
歌川広重は、江戸時代の後期に活躍した浮世絵師になり、当時の旅行ブームに乗っかり東京から京都までの東海道すべての宿駅を描いた「東海道五十三次」が最も有名な作品として、高く評価されています。実は武家の出身であり、生粋の江戸っ子としても知られ... -

歌川豊国
歌川豊国は、江戸時代に活躍した浮世絵師になり、本名は倉橋熊吉といいました。江戸の三島町に生まれ木彫りの人形師の息子として生まれます。幼少期に歌川派のもとで学んだこともあり、その後、歌川豊国の名前を名乗るようになりました。1794年に描いた「... -

大田垣蓮月
大田垣蓮月は、江戸時代の末期から明治にかけて活躍しました。京都で生まれ、生後10日には養女となり、知恩院で生まれ育ちます。出家したあと、養父が亡くなったタイミングで引っ越し、その後転々とした生活をしました。大田垣蓮月は、岡崎に引っ越しした... -

大山忠作
大山忠作は、福島県二本松市出身の画家です。代表作は「五百羅漢」や「池畔に立つ」などになり、第2回の日展で初入選をはたします。人物画はもちろん、宗教的な作品もあり、花鳥風月などの題材をメインに描きました。大山忠作は、あくまでも描きたいものを... -

岡倉天心
岡倉天心は横浜で生まれましたが、福井県出身の武士の家系で、家族で東京に移り住みました。9歳のとき母が亡くなり葬儀をおこなった長延寺に預けられると、英語なども学びます。1882年に専修学校での教官になり、学校創立の繁栄にも貢献したと言われていま... -

奥村政信
奥村政信は、江戸時代前期に活躍した浮世絵師です。源八郎と呼ばれ人生のうち50年間もさまざまな作画を作り続けました。ジャンルの幅も広く、丹絵や紅絵、漆絵などの浮世絵を描き、画風を常に変化させていました。奥村政信は、そのときの時代で流行ってい... -

小倉遊亀
小倉遊亀は、1895年に滋賀県で生まれ、日本で初めて日本美術院の同人に認められた人物です。日本を代表する画家としても知られており、教諭なども務めました。小倉遊亀は、日本芸術院会員になり、安田靫彦に師事していたことでも知られています。105歳とと... -

織田一磨
織田一磨は、1882年に東京府芝区にて誕生し、その後、大阪に転居しています。主に明治から唱和にかけて活躍した芸術家でもあり、版画家として知られています。洋画は川村清雄から学び、石版は金子政次郎より学び、京都の新古美術展にて初めて作品を発表す... -

尾竹竹坡
尾竹竹坡は、明治から昭和にかけて活躍した、浮世絵師であり日本画でも有名な人物です。新潟市で生まれ5歳の頃には襖絵などを描き、6歳には花鳥画を丁寧な執筆で書き上げるなど、早くからその才能を認められ神童と呼ばれていました。尾竹竹坡が10歳の頃に... -

落合芳幾
落合芳幾は、幕末から明治にかけて活躍した浮世絵師です。1833年に日本堤下の茶屋にて生まれ、質屋に奉公していたものの子供の頃から絵に強い興味を持っていたそうです。1849年には歌川国芳に入門し、安政の大地震にて妻子を失った惨状を絵に描いたことで... -

小野竹喬
小野竹喬は、1889年に岡山県の笠岡市にてうまれ、その後京都に上り絵画専門学校の別科に入学します。1916年には文展にて「島二作」が特選を受賞するなど早くから高く評価されました。小野竹喬は、近代的な日本画を代表する画家でもあり、89歳で亡くなるま... -

恩地孝四郎
恩地孝四郎は、明治から昭和にかけて活躍した、版画師であり、写真家や詩人など多様な才能を生かし成功した人物です。なかでも創作版画は先駆者のひとりとしても知られており、日本に版画の認知を高めたことでも知られています。恩地孝四郎は、1891年に4男... -

懐月堂安度
懐月堂安度は、詳しい生没年不詳の画家になり、江戸時代の初期に活躍したと考えられている浮世絵師になります。江戸に生まれ浅草の蔵前に住んでいました。懐月堂安度は、弟子を多く抱えており、吉原の遊女などを題材にした肉筆画の美人画が多く残されてい... -

勝川春章
勝川春章は、江戸時代中期に活躍した浮世絵師です。役者絵を中心に、特徴をしっかりと捉えた似顔絵のような作品を次々に生み出したことでも知られています。1774年に誕生しますが、本姓などはわかっていません。勝川春章は、絵を宮川春水に学び、北尾重政... -

勝川春亭
勝川春亭は、江戸時代の後期に活躍した浮世絵師です。勝川春英の門人でもあり、武者絵や役者絵にとどまらず、美人画や名所絵なども残し、さまざまな絵のジャンルに挑戦したことでも知られています。勝川春亭は、挿絵も数多く残していますが、最も多いのは... -

勝川春英
勝川春英は、江戸時代に活躍した浮世絵師になり、家系などの詳しい情報はわかっていません。17歳で初作を描くと役者絵なども多く、たくさんの作品を世に出しました。1792年には「大坂中の芝居」と呼ばれる四枚続を版行し、役者大首絵を複数刊行したことで... -

鏑木清方
鏑木清方は、明治時代から昭和に活躍した美人画家として知られ、生涯にわたり、江戸や東京に関する作品を数多く残したことでも知られています。東京の神田で生まれ、父親はジャーナリストだったそうです。最も有名なものといえば、「築地明石町」になり、... -

狩野探幽
江戸狩野派の始祖として知られる絵師といえば「狩野探幽(かのうたんゆう)」ではないでしょうか。京都で生を受け、狩野孝信の長男として誕生しました。 徳川家御用達の絵師として活躍するなど、たくさんの代表作を世に送り続けています。狩野探幽とはどん... -

川合玉堂
川合玉堂(かわいぎょくどう)といえば、日本の山や河などの自然の美しさを愛し数々の作品を残してきた画家です。絵の一つ一つから温かさが感じられ、風景を後世にしっかりと伝えてくれます。おおらかさも感じられるのは玉堂の人柄あってのことかもしれま... -

川上澄生
川上澄生は、1895年に神奈川県で生まれた日本の版画家です。幼少期から芸術に触れていたわけではなく、青山学院の高等科に在籍していたときに木口モクバンの合田清と出会います。主に、オランダ文化が日本に取り入れられたことが、作品に影響していると言...