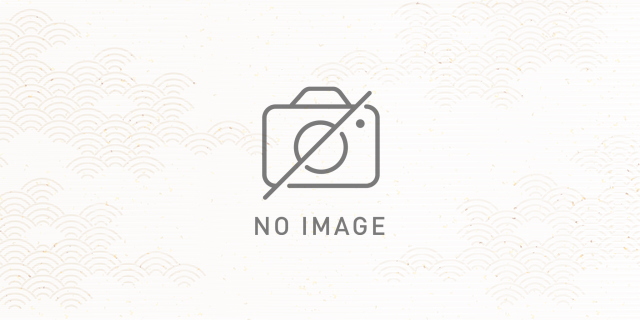陶磁器– category –
-

丹波焼
丹波焼(または丹波立杭焼)は、兵庫県丹波篠山市今田町立杭地区で焼かれる陶器で、日本六古窯の一つに数えられます。その歴史は平安時代末期から鎌倉時代初期に遡り、800年以上にわたり生活用器を中心に作られてきました。最大の特徴は、桃山時代以降に導... -

信楽焼
信楽焼は、滋賀県甲賀市信楽町を中心に、約1260年の歴史を持つ日本六古窯(にほんろっこよう)の一つです。特に鎌倉時代以降、茶の湯の発展とともに茶道具として重宝され、広く知られるようになりました。最大の特徴は、良質な信楽の土が生み出す素朴で暖... -

京焼
京焼とは、京都で生産される陶磁器の総称です。特に清水寺の参道で作られていた清水焼が代表的で、現在では京焼・清水焼として知られています。都として栄えた京都で、公家や茶人の嗜好品として発達したため、特定の様式にこだわらず、各地の優れた技術や... -

常滑焼
常滑焼(とこなめやき)は、愛知県常滑市を中心に知多半島で焼かれる炻器(せっき)で、日本六古窯の一つに数えられます。その起源は平安時代末期にさかのぼる、長い歴史を持つ焼き物です。初期の特徴: 古代から大甕(おおがめ)や壺などの大型の日用雑器... -

瀬戸焼
瀬戸焼(せとやき)は、愛知県瀬戸市周辺で生産される陶磁器の総称で、日本六古窯の一つです。その歴史は1000年以上と古く、古くから焼き物といえば「せともの」と呼ばれるほど、日本の陶磁器の代名詞的存在でした。歴史: 平安時代末期に施釉陶器(ゆうや... -

萩焼
萩焼(はぎやき)は、山口県萩市一帯で作られる伝統的な陶器です。豊臣秀吉の朝鮮出兵の際に朝鮮から連れてこられた陶工が開窯したのが始まりで、茶陶(茶の湯の道具)として特に高い評価を受けてきました。素朴な土の風合い: ざっくりとした焼き締まりの... -

有田焼・伊万里焼
有田焼と伊万里焼は、17世紀に有田で誕生し、伊万里港から積み出されたことで共通の歴史を持ちますが、現在の産地と作風で区別されています。有田焼(佐賀県有田町): 主として白磁の美しさを基盤とし、柿右衛門様式の繊細な色絵や、古伊万里様式(金襴手... -

九谷焼
九谷焼(くたにやき)は、石川県加賀市周辺を産地とする、日本を代表する色絵磁器です。江戸時代前期に加賀藩の命により開窯されたのが始まりで、この時期の作品は特に古九谷(こくたに)と呼ばれ珍重されています。九谷焼の最大の魅力と特徴は、その豪華... -

美濃焼
美濃焼(みのやき)は、岐阜県東濃地方(主に多治見市、土岐市、瑞浪市、可児市)で製作される陶磁器の総称です。日本の陶磁器生産量の約半数を占める、国内最大の生産地です。最大の特徴は「特徴のなさ」とも言われる多様性にあります。定まった様式を持... -

益子焼
益子焼(ましこやき)は、栃木県益子町周辺で生産される伝統的な陶器です。江戸時代末期に窯業が始まり、当初は水がめや土瓶などの日用品を中心に制作され、関東の台所を支えました。大きな特徴は、地元の土を用いた、厚手でぽってりとした素朴で温かみの... -

磁器
磁器(じき)は、陶磁器の一種で、主に陶石やカオリンといった岩石を砕いたものを主原料とする「石もの」です。特徴として、1250℃以上の高温で焼かれるため、素地がガラス質化し、非常に硬く締まります。これにより、吸水性がほとんどなく、強度が高いため... -

陶器
陶器(とうき)は、陶磁器の一種で、主に山や田畑から採れる粘土(陶土)を原料として作られる「土もの」です。特徴としては、焼成温度が比較的低い(約800℃〜1200℃程度)ため、焼き上がりの素地が完全にガラス化せず、きめが粗く吸水性がある点が挙げられ... -

陶磁器
陶磁器は、陶器(土もの)と磁器(石もの)の総称です。主に粘土や陶石などの土の成分を原料とし、高温で焼き固めて作られます。 陶器は、粘土を主原料とし、比較的低い温度で焼かれます。素地には吸水性があり、軽く叩くと鈍い音がします。暖かみのある風... -

浅蔵五十吉
大正2年に石川県の寺井町にて生まれました。小学校を卒業したあとに陶芸の技術を父親から学び、その後、昭和3年に初代「徳田八十吉」氏に師事したといわれています。また、昭和21年には「北出塔次郎」氏にて色絵の技術を学び習得していきます。同じ年に行... -

浅見隆三
明治37年に京都東山に生まれ、本名は柳三といいます。三代浅見五良助の次男として生を受け、陶技は祖父より手ほどきを受けました。大正12年京都市立美術工芸学校図案化を卒業したあと、関西美術院にて洋画を学びました。昭和4年の帝展にて「三葉紋花瓶」で... -

石黒宗麿
1893年に富山県の新湊市に生まれました。地元の中学を中退し上京したあと中越汽船会社にて勤務し、楽焼を通して陶芸に触れたことで興味を持ったといわれています。その後、金沢に移り住んだあと伊賀や三嶋などの焼き物に触れました。京都に拠点を移し、パ... -

伊勢崎淳
岡山県備前市伊部に、伊勢崎陽山の次男として生まれました。同じ陶芸家の満とともに姑耶山に中世の半地下式穴窯を復元したことでも知られています。1959年には岡山大学教育学部特設美術科を卒業し、父と一緒に作陶の世界に入りました。1966年には日本工芸... -

市野雅彦
昭和36年に兵庫県篠山市生まれの陶芸家です。丹波立杭の茶陶作家 初代市野信水を父に持ち、次男として生を受けました。市野雅彦氏の兄は「二代目信水」として認定されており、兄弟そろって確かな功績を残している人物です。広島にて陶芸を学んだあとに、故... -

井上良斎
1888年(明治21年)に東京浅草に生まれた陶芸家です。本名は井上良太郎といい、隅田川の川べりに窯を築き、陶工良斎の業を担いました。錦城中学校に進学した辺りから従事するようになり、三代目となりました。技術を研磨し続けた結果、青や白の陶磁器や緑... -

今井政之
1930年に大阪府大阪市で誕生した陶芸家です。1943年に父親の故郷である広島県に移り住み、その後、広島県立竹原工業学校を卒業し、備前焼の修行に従事しました。1952年には、拠点を京都に移し初代勝尾青龍洞に入門しています。翌年1953年には、発揮人とな... -

岩田藤七
1893年に東京日本橋本町の呉服商の家に生まれました。幼名は東次郎といい、1911年に商工中学校を卒業したあと、1911年白馬会で岡田三郎助に師事して洋画を学びました。1918年東京美術学校金工科に入学すると彫刻を海野勝珉氏に学び、1923年西洋画科を卒業... -

永楽善五郎
永楽善五郎の永楽家は、千家の伝統的な茶道具を制作している一家として知られています。京焼の家元として代々受け継いできた文化があり、千家十職の一つ「土風炉・焼物師」を制作しています。初代は大永の時代になり9代目までは「西村姓」と名乗り、10代目... -

尾形乾山
尾形乾山は、1663年に京都の呉服商の三男として生を受けました。尾形光琳は、実の兄となり兄弟仲は良かったものの、性格が対照的で堅実な性格をしていたと言われています。暮らしも質素で、読書家としても知られています。37歳のときに尾形兄弟に興味を持... -

岡部嶺男
岡部嶺男は、1919年に愛知県瀬戸市に誕生しました。 加藤唐九郎の長男として父親の背中を見て育ちます。愛知県立瀬戸窯業学校を卒業し、1940年東京物理学校を中退し岡部辰子と結婚し、愛知県愛知郡日進町に新居を構えて生活するようになります。 青瓷、織... -

隠崎隆一
隠崎隆一は、人間国宝としても認定された陶芸作家です。自由な発想を大切にして独自の表現を用いて、備前焼で新しい道を切り開き自身の地位を確かなものにしました。昭和25年に長崎県で生まれ、大学ではデザインを深く学びました。瀬戸内市長船町磯上に窯... -

鹿児島寿蔵
鹿児島寿蔵は、1898年に福岡県福岡市に誕生しました。高等学校を卒業したあとに、井上式地理歴史標本作成所に所属して模型の制作や色彩に尽力しました。当時、工場長だった有岡米次郎が独立したときに、博多人形のノウハウを学び、1917年に自分の窯を構え... -

加藤卓男
1917年に五代加藤幸兵衛の長男として誕生しました。1961年にはフィンランド工芸美術学校を修了し、日展で第六回北斗賞も受賞しました。古代ペルシア陶器ならではの独創的で色彩豊かな、釉調に魅力を感じ、イラン・パーレヴィ王立大学付属アジア研究所留学... -

鎌田幸二
鎌田幸二は、1948年に京都生まれの陶芸家です。京都府立桃山高等学校を卒業したあとに、京都府立陶工訓練校専攻科修了しています。きっかけとなったのは、五条坂の清水正氏になり指導を受けその後、京都府技師として指導員になりました。五条坂共同登窯「... -

川北良造
川北良造は、石川県出身の木工芸家です。木工芸科は、重要無形文化財として認められています。挽物の産地として有名な山中氏市にて生まれ、師事しています。その後、氷見晃堂に師事し、伝統的にも高い技術を持っていることが認められていました。比較的シ... -

金城次郎
金城次郎は、沖縄県の陶芸家として知られています。国の重要文化財である琉球陶器の技術保持者としても知られており、沖縄県で初の人間国宝として認定されました。13歳のときに新垣栄徳が、民芸運動を展開していた濱田庄司や柳宗悦の影響を強く受け製作... -

楠部彌弌
楠部彌弌は、1897年に京都市東山区にて生まれました。本名は「彌一」といい、楠部貿易陶器工場を経営する楠部千之助の四男として生を受けました。1912年には京都市立陶磁器試験場付属伝習所に入所し、1915年に陶磁青年会主催の展覧会で受賞しました。1918... -

熊倉順吉
熊倉順吉は、大正9年に京都府東区に生まれた陶芸家です。人間のエロスを表現とした手法を陶影した作品を得意としていました。ジャズにも深い関心を示しており、口元は最も人間らしい部分だと表現しています。昭和13年京都市立第一工業学校建築科を卒業した... -

黒木国昭
宮崎県須木村出身のガラス職人として知られており、宮崎県立小林高等学校卒業と同時にガラス会社に就職してガラスの世界に入ります。1991年には国の卓越技能者「現代の名工」に認定されています。もともとガラスは西洋の素材として知られていますが、日本... -

鯉江良二
鯉江良二は、1938年に愛知県常滑市にて生まれた陶芸家です。歴史ある土地だからこそ、窯業に興味を持ち、志すようになります。愛知県立常滑高等学校窯業科卒業したあと、日本タイルブロック製造株式会社に入社します。14歳のときにアルバイトによって右手... -

坂倉新兵衛
坂倉新兵衛は、萩焼の宗家として350年の歴史を持っています。山口県長門市深川の窯元として知られており、当主が代々襲名している名前です。1974年に作陶の世界に踏み入れ、東京芸術大学美術学部彫刻科を卒業したあと、大学院にて陶芸を専攻し終業していま... -

坂高麗左衛門
坂高麗左衛門は、山口県萩市で代々襲名してきた陶芸の家元です。400年以上の歴史を持ち、伝統の様式を守りつつ歴史が積み重ねてきたものを大切にしています。当代は十四代目になり毛利輝元によって、荻の地に連れてこられたと言われています。兄李勺光と共... -

館林源右衛門
館林源右衛門は、佐賀県西松浦郡出身の陶芸家です。本名は、金子源といい、佐賀県立有田工業学校窯業科を卒業と同時に家業の源右衛門窯で従事するようになります。源右衛門では、手描きならではの美しさにこだわり、一つとして同じものはありません。伝統... -

田端志音
田端志音は、1947年に福岡県北九州市で生まれた陶芸家です。現在は自宅にて個展を開催するなど、精力的に活動していることでも知られています。1985年より5年間江戸時代から続く大阪の道具商「谷松屋戸田商店」に勤めたことが、きっかけとなり陶芸の道に進... -

田村耕一
田村耕一は、栃木県佐野市出身の陶芸家です。東京美術大学にて陶芸のノウハウを学んだあと、大阪に移り楽焼に触れました。戦後に松風工業株式会社松風研究所に入所したあと、陶芸の本格的な研究を行うようになります。 ・昭和33年 現代日本陶芸展で朝日賞... -

沈壽官 15代
沈壽官は、鹿児島県で400年以上の歴史を持った「薩摩焼」の当主が歴代受け継いできた名称です。もともとは豊臣秀吉が朝鮮に出兵したときに連れて来られた者になり、今でも薩摩焼の伝統を今に伝えている存在と言えるでしょう。精緻な装飾陶器や、薩摩切子の... -

塚本快示
1912年岐阜県生まれの陶芸家です。昭和初期に「青白磁」を作り出した第一人者としても知られており、国の重要無形文化財(人間国宝)として認定されています。本名は快児といい、江戸中期から続く未納焼の窯元になり、小学校を卒業したあと長男として家元... -

辻清明
辻清明(つじせいめい、1927-2008)は、昭和から平成にかけて活躍した陶芸家です。現代陶芸の発展に大きな影響を与え、特に信楽焼(しがらきやき)の伝統を継承しつつ、独自の造形美を追求しました。修行と拠点: 京都府出身。走泥社(そうでいしゃ)の創立... -

坪島土平
1929年大阪府出身の陶芸家です。大阪市立錦城商業学校を卒業したあとに、1946年に川喜田半泥子に師事し陶芸の技術を磨いていきます。1963年に川喜田が亡くなったあとに、廣永陶苑を継ぎ、毎年のように個展を開催するようになりました。津市の広永窯におい... -

徳田八十吉
徳田八十吉は、石川県で代々受け継いできた九谷焼の陶芸家です。1933年に二代目徳田八十吉・魁星の長男として生を受け、1988年に三代目を襲名したといわれています。初代徳田八十吉の初孫だったこともあり、かわいがられて育ったといわれています。金沢美... -

中里太郎右衛門
中里太郎右衛門は、佐賀県の唐津市で420年以上の歴史を持った唐津焼の窯元のことをいいます。江戸初期に作陶を始めた中里又七をはじめ、唐津焼御茶碗窯(おちゃわんがま)を代々継承してきました。現在の三代目は1957年に十三代の長男として生を受け、武蔵野... -

中島宏
中島宏とは、1941年に佐賀県で生まれた陶芸家です。中学校を卒業したあとに、父親の工房に入って焼き物の修行を始めました。69年に弓野古窯跡に窯を築き独立すると、青磁器の創作に精力的に取り組みました。今までの青磁器のイメージを変えるような、独... -

並河靖之
並河靖之は、明治時代に七宝作家として活躍した陶芸家です。1845年に川越藩の家臣「高岡九郎左衛門」の三男として京都に生を受けます。11歳のときに親戚の養子となり、家督を継ぐと1873年には宮家に仕えながら、七宝業に取り組むようになります。1875年に... -

原清
原清は、1936年に島根県で生まれた陶芸家です。この辺りは出雲と呼ばれている地域になり、当時から港に陶器を乗せた船が立ち寄ることもあり、幼少期より陶器に触れる機会が多かったといわれています。陶器の世界に興味を持ったのも、登下校中に見かけた陶... -

福島武山
福島武山は、石川県金沢市生まれの陶芸家です。先人が築いてきた技術を現代によみがえらせたことでも知られており、小紋や花鳥、風月、人物を古典的な柄を赤一色で描いていることが特徴です。繊細なタッチで描かれているのは、福島武山ならではと言えるで... -

藤原和
藤原和は、人間国宝藤原雄の長男として備前市に生まれました。明星大学修了後に帰郷したことで、祖父や父に師事し陶芸について学びました。その影響を受け、藤原和の作る作品は「単純」「明快」「豪快」である特徴を持ち合わせています。1983年には京都知... -

藤原雄
藤原雄は、1932年に岡山県備前市で生まれた陶芸家です。藤原啓、勝代の長男として生まれたが、もともと視力が右目は0.0.、左目は全くないという状態だったものの、父親の意向として健常者として育て進学させたいとこだわったため、55年には明治大学文学部...
12