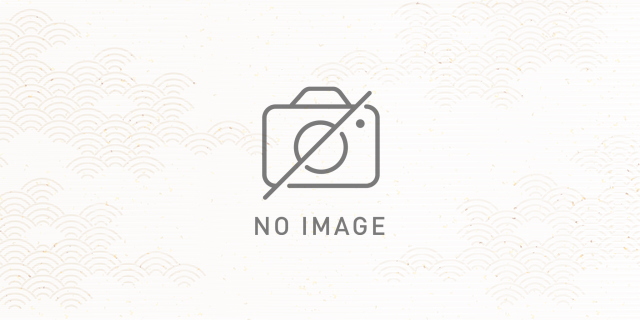「蓋置(ふたおき)」は、茶道で茶釜の蓋や、湯を汲む柄杓(ひしゃく)の合(ごう:水をすくう部分)を一時的に置くために用いられる、小さな台です。
炉(ろ)や風炉(ふろ)のそばに置かれ、点前(おてまえ)を円滑に進めるための重要な役割を果たします。
主に竹、陶磁器、金属などで作られ、季節や道具の取り合わせによって使い分けられます。
竹製:一般に風炉の時期(5月〜10月頃)に多く用いられます。竹の節目を生かして作られる「引切(ひききり)」などが代表的です。
陶磁器・金属製:主に炉の時期(11月〜4月頃)に用いられます。
非常に小さいながらも、その素材や意匠(「一閑人」「蟹」「三つ葉」など)には亭主の趣向や季節感が凝らされており、茶の湯における美意識と実用性を兼ね備えた道具です。
TEL0120-554-110