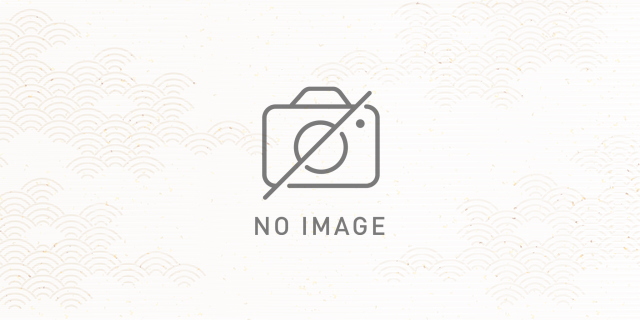茶杓(ちゃしゃく)は、茶入から抹茶をすくい取り、茶碗に入れるための細長い匙(さじ)です。竹を削って作られるものが主流であり、その一本の竹の中に「侘び寂び」の美意識と茶人の心が凝縮されています。
素材と形状: かつては象牙などが用いられましたが、千利休の時代以降は竹製が主流となり、利休は竹の節を中央に残す中節(なかぶし)を好みました。竹の色合いや節の位置、自然な曲がり(撓め)の美しさが鑑賞のポイントです。
各部の見どころ: 抹茶をすくう先端は櫂先(かいさき)、その裏の溝を樋(ひ)と呼びます。櫂先の削り方や、茶杓の末端である切止(きりどめ)の仕上げに、作者の個性が表れます。
銘(めい): 茶杓は単なる道具ではなく、季節の情景や禅の精神にちなんだ銘が付けられることが多く、茶会ではその銘によって趣向が深まります。茶杓を収める筒に記された銘も含め、茶人にとって刀剣にも匹敵する「茶人の刀」とも称されるほど重要な道具です。
TEL0120-554-110