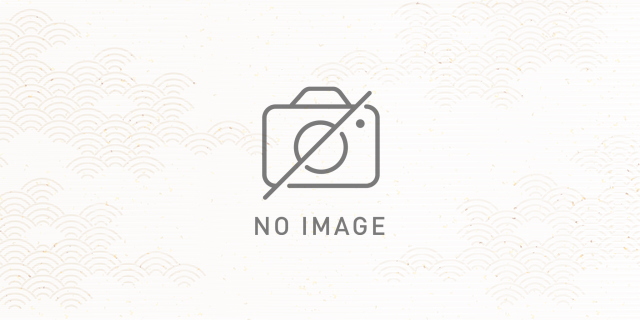1893年に富山県の新湊市に生まれました。地元の中学を中退し上京したあと中越汽船会社にて勤務し、楽焼を通して陶芸に触れたことで興味を持ったといわれています。その後、金沢に移り住んだあと伊賀や三嶋などの焼き物に触れました。京都に拠点を移し、パリ万博の博覧会では銀賞を受賞したこともあります。
鉄釉にかかわる宋磁研究をテーマにして、品格の高い作品を次々に発表していきました。なかでも、唐三彩、均窯、絵高麗、三島、唐津にて優れた技術を示し、大きな影響を与えたことでも知られています。1955年2月に鉄釉陶器の重要無形文化財保持者(人間国宝)の認定を受け、社団法人日本工芸会の理事に就任し伝統工芸の振興に努めました。1956年(昭和31)年2月には富山県新湊市名誉市民、1963年(昭和38年)11月、紫綬褒章を受章、勲三等瑞宝章を受章するなど輝かしい経歴を残しています。
身体障害者や精神薄弱児、母子家庭、保育園など社会福祉にも力を入れていましたが、75歳で亡くなりました。豪快なエピソードも多く、身に着けるものにもこだわりお金を湯水のように使う一面もありましたが、陶芸には一切の妥協を許さない人物だったそうです。