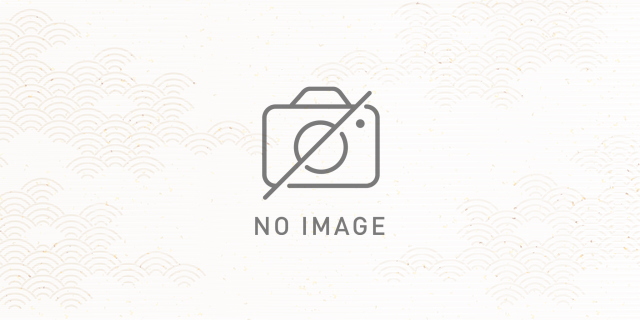和泉の国境で生まれ、江戸時代の真言宗の僧侶として活躍した人物になります。文化人としても有名な人になり、陶芸はもちろん、茶道や絵画、書道などに長けていたそうです。なかでも能書家としても高く評価され、独自の松花堂流などの書風を編み出したことでも知られています。その才能からも寛永の三筆なんて呼ばれることもありいかに期待されていたのかがわかると思います。松花堂弁当の名前の由来になったとも言われているなど、陶芸家としても文化人としても素晴らしい人物です。
布袋図などが有名なため茶器の作品は少ないのが残念です。茶の湯を好んでいたこともあり、数々の有名な茶器を持っていたそうです。そのことを称して「八幡名物」などと呼ばれ親しまれています。