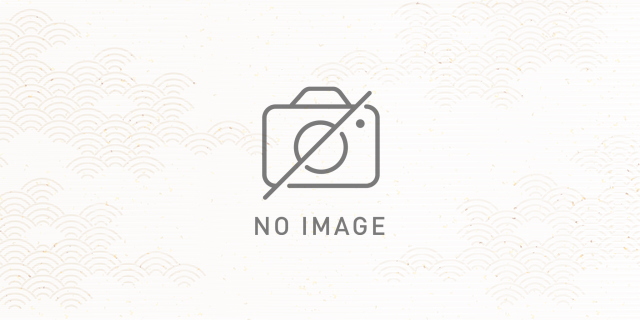石川県金沢市で生まれた、陶芸家でもあり蒔絵師としても認められた人物です。7歳のときに蒔絵に出会い修行を始め、東京美術学校漆工科にて技術を学びます。その後、母校に教授として就任し、教鞭をとったことでも有名です。1955年には人間国宝として認められ、伝統工芸の復興に尽力していました。蒔絵の万年筆制作なども有名で、漆の工芸品にその名を残す有名な人物でもあります。1963年には文化交流を受賞、1978年には金沢名誉市民、1983年には輪島名誉市民にも認められています。90歳で亡くなるまで陶芸の道を極め続けたことでも有名です。
草花鳥獣門小手箱や、槇柏蒔絵手箱、有職文蒔絵螺鈿飾箱など数々の作品が残されています。なかでも桜流水文神代欅棗の美しさはひとしおで、時代を超えて愛されています。