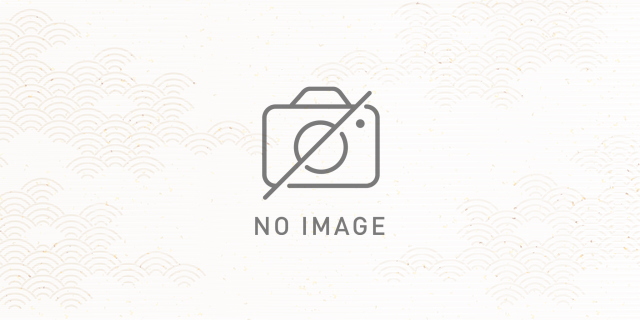瀬戸焼(せとやき)は、愛知県瀬戸市周辺で生産される陶磁器の総称で、日本六古窯の一つです。その歴史は1000年以上と古く、古くから焼き物といえば「せともの」と呼ばれるほど、日本の陶磁器の代名詞的存在でした。
歴史: 平安時代末期に施釉陶器(ゆうやくをかけた陶器)の生産が始まり、鎌倉時代には中国の技術を取り入れた古瀬戸が発展しました。
特徴: 陶器と磁器の両方が生産されており、「瀬戸で焼けないものはない」と言われるほど多様です。特に、鉄分が少ない良質な陶土と多様な釉薬(ゆうやく)により、白く美しい素地と多彩な色付けが可能です。
代表的な釉薬: 現在は美濃焼の様式にも含まれる黄瀬戸、瀬戸黒、志野といった桃山陶の技術も、元は瀬戸の窯で発展したものです。
TEL0120-554-110