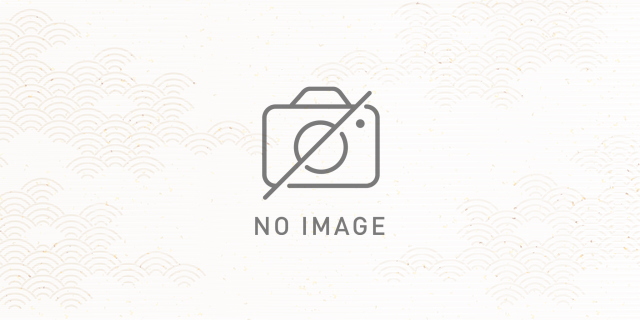木彫りは、木材を素材として彫刻刀やノミなどの工具を用いて形や模様を彫り出す技法、またはその作品自体を指します。石や金属に比べ、温かみのある質感と、彫りやすく加工しやすいという特性を持ち、古くから世界中で用いられてきました。
日本では、飛鳥時代に仏教が伝来して以降、仏像の制作に広く用いられ、特にヒノキやクスノキなどが使われてきました。一本の木から彫り出す一木造(いちぼくづくり)や、複数の木材を組み合わせて作る寄木造(よせぎづくり)などの技法があります。
鎌倉時代の運慶・快慶による金剛力士像は躍動感あふれる木彫の傑作として知られ、また、社寺の欄間(らんま)彫刻や、北海道の木彫りの熊などの民芸品まで、その用途は多岐にわたります。木目や素材の持つ力を生かした表現が大きな魅力です。
TEL0120-554-110