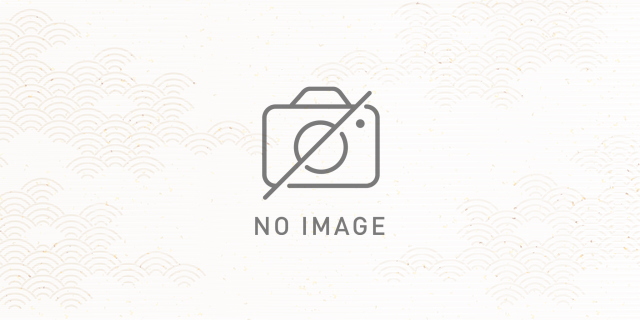伊藤若冲(いとう・じゃくちゅう)
江戸時代中期の画家。京都の青物問屋(野菜の問屋)の跡継ぎとして生まれた伊藤若冲は、家業を継ぎつつも絵を描くことに熱中し、40歳になったときに家督を譲って画家としての道を歩み始めました。
専業画家になる前から、家業でなじみが深かった植物や動物をよく観察し描き続けていたため、動植物の姿を生き生きと描き出す画風を既に身につけていた若冲。その作品は、ありのままの自然を精緻な筆で描くという他に類を見ない個性を持った作家です。
博物館所有の作品も多く、未だに多数の展覧会が開かれるなど、多くの日本人から愛されています。2019年には、個人所有の伊藤若冲の作品が見つかり、博物館が購入したとニュースになりました。
伊藤若冲の作品は、各地の博物館や寺で見ることが出来ますが、公開期間が決まっているものも多いため、日程を調べてから訪問することをお勧めします。
【作品紹介】
・「群鶏図」
若冲といえば鶏をイメージする方が多いのは、このような精緻な群鶏画の印象が強いからではないでしょうか?
10羽以上の鶏が描き分けられているこの作品は、1匹1匹が緻密に描き込まれており、また今にも動き出しそうな躍動感を持っています。長年動植物の観察を続け、模写を行ってきた若冲ならではの作品と言えるでしょう。
・「樹花鳥獣図屏風」
若冲の作品はどれも個性的ですが、この作品はさらに特別な手法を用いて描かれています。
「升目描き」や「モザイク画法」と称される手法で描かれたこの屏風は、画面に無数の方眼を作って彩色し、色や陰影を付けて立体感を感じさせるという特殊な作品です。
一対の屏風の右隻に「白像」を、左隻に「鳳凰」を描き、実在の生き物から空想上の生き物までが様々に配置されています。デジタルアートにも見えてくるこの作品は、Eテレの番組「びじゅチューン!」でも紹介されました。
・「象と鯨図屏風」
カラフルな絵だけでなく水墨画もたしなんだ伊藤若冲の晩年の作品です。屏風の右隻には陸地の王者「白象」を、左隻には海上の王者「黒鯨」を、脈動感をもって描いています。
白と黒という対比、そして陸と海という対比があり、その中に強大な二匹の動物がどっしりと構える構図が印象的。北陸の旧家に伝わったこの屏風は、2008年に存在が知られ、現在は博物館の所有となっています。