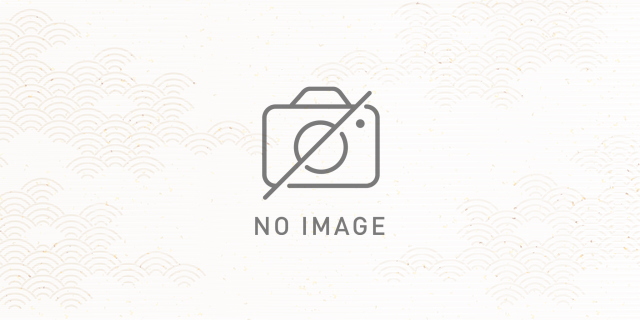茶道具– category –
-

濱田庄司
昭和に活躍した、比較的新しい時代の陶芸家でもあります。神奈川県の溝の口で生まれ、高等工業学校の窯業科に入学し、基礎全般を学びます。卒業したあとは、河合寛次郎と一緒に京都の陶芸試験場にて研究を行います。1923年には個展を開き、帰国し沖縄で生... -

飛来一閑
一閑張細工師の分野として千家十職で認められている職種になります。この分野での創始者でもあり、代々が細工師として受け継がれてきた家系です。もともと非来家亡命明人の末裔であると考えられ、清の侵略の広がりによって、身の危険を感じたことで日本に... -

藤本能道
日本の陶芸家でもあり、重要無形文化財保持者として知られています。もともと東京の新宿区に生まれ、東京美術学校工芸科図案部を卒業したあと、文部省の技術講習所に入ります。1938年には富本憲吉の助手を務め、九谷焼などの技術を取得します。技術指導を... -

藤原啓
兄弟で陶芸家として活躍し他人物になり、岡山県の備前市出身です。名誉県民としてもその名を知られています。子供のときから俳句や小説などの文才を発揮し1等を獲得。これをきっかけに上京し、編集部に勤務し担当を持つまでになります。編集を学び、作家と... -

古田織部
武将でもあり芸術家として知られた人物になり、主に戦国時代から江戸時代にかけて活躍しました。茶道織部流の祖としても知られるようになり、織田の家臣として仕えた記録も残っています。武士としての実績は少ないながらも的確な意見でアドバイスをするな... -

細川護熙
日本の政治家として活動した人物になり、新聞社や参議院議員、県知事、内閣総理大臣など目覚ましい活動をしました。還暦のときに政界を引退し、その後は陶芸家や茶人などの活動を行っていたそうです。祖母の住まいがあった神奈川県の湯河原で「不東庵」を... -

松井康成
長野県佐久市出身の陶芸家です。戦時中には茨城県に疎開し、卒業後に、奥田製作所にて陶芸の技術を学び習得します。大学を卒業したあとに月崇寺の住職になり、窯を作り研究を続けたといいます。とても探究心の強い人物になり、田村耕一のもとで学んでいた... -

松平不昧
出雲の松江藩の七代目を務めた人物になり、江戸時代の代表的な茶人として知られています。今でも一目置かれる存在として名高く伝えられています。当時、松江藩は財政が破産しており厳しい状態でした。そこに藩政改革に乗り出し農業政策や治水工事を行い、... -

松田権六
石川県金沢市で生まれた、陶芸家でもあり蒔絵師としても認められた人物です。7歳のときに蒔絵に出会い修行を始め、東京美術学校漆工科にて技術を学びます。その後、母校に教授として就任し、教鞭をとったことでも有名です。1955年には人間国宝として認めら... -

宮川香山
京都に生まれ、もともと陶芸家である真葛宮川長造の四男でした。19歳のときに家督を継ぐと、当時「香山」としての称号を受けていたことから、その名前で活動するようになります。色絵の陶磁器や磁器などはもちろん、薩摩焼などの研究も行います。幕府から... -

三輪休和
山口県萩市に生まれ、人間国宝にも指定されている人物です。荻藩御用達の窯三輪家の次男として生まれます。中学校に入学するも、職人に学問はいらぬという考えのもと、2年で退学してしまいます。その後家業に専念し、茶道なども含め諸芸を学ぶことに尽力し... -

楽吉左衞門
千家十職の一つとして、楽焼を使った茶器を制作しています。初代の長次郎は、創設者の父のもとで生まれ黒軸をかけた茶碗制作で高い才能を発揮します。「樂」は豊臣秀吉から与えられたものになり、楽焼の始まりになったと言われています。田中姓を持ってい...
12